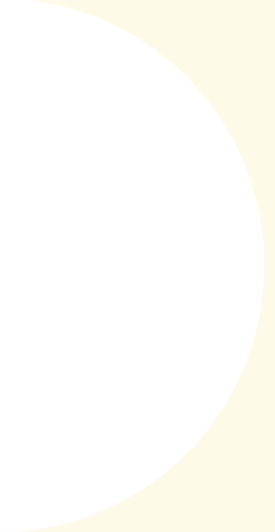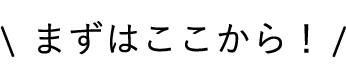保育士の人手不足が問題となっておりますが、保育士になりたくても、「忙しくて有給が取れないのでは?」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか?
また、勤めている保育園で休みがとりづらく、悩んでいる保育士さんもいるかもしれません。
そこで今回は、保育士の有給休暇について詳しく解説していきます。
有給休暇の日数やもらえる条件、取れない場合の対策などもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
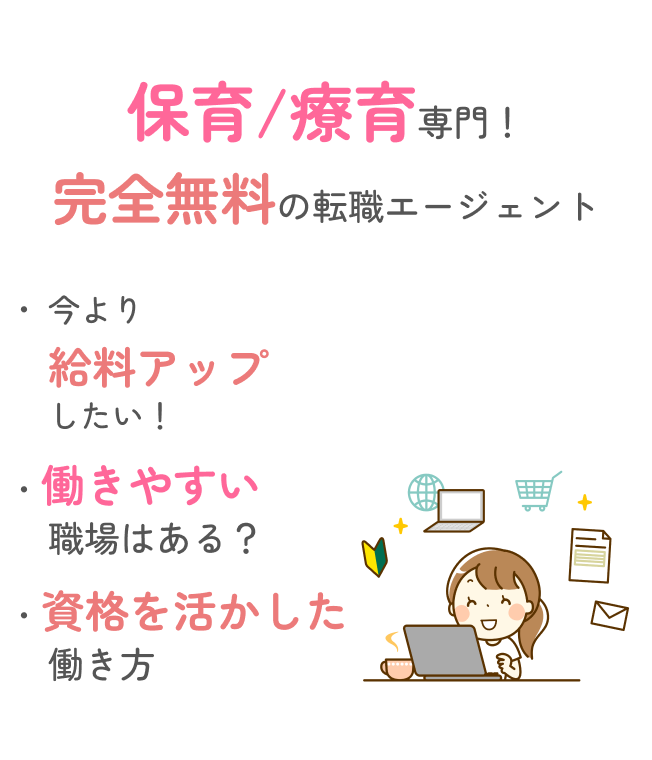

保育士の有給休暇はどのくらいもらえる?
有給休暇とは、正式には『年次有給休暇』と呼ばれ、労働基準法第39条によって定められている労働者の権利です。
労働基準法の規定では、働き始めて6ヶ月を超えた場合、10日間の有給休暇が付与されると決められています。
勤続年数ごとの有給付与日数は下記のとおりです。
| 勤続年数 | 有給付与日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
勤続年数が6年6ヶ月を超えると、付与日数は20日となります。つまり、10年、20年と勤務した場合も付与される日数は20日です。(法人によってそれ以上の場合もある)
また、この後詳しくご紹介しますが、有給休暇は雇用形態に関わらず支給されるものです。要件を満たしていれば、パートやアルバイトでも付与されますが、労働日数に応じて付与される日数は異なります。
なお、週所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の労働者に付与される日数は次のとおりです。

参考: 厚生労働省 「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
有給休暇がもらえる条件はあるの?
有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトの方でも付与がされていれば取得可能です。
ただし、すべての人がもらえるわけではなく、労働基準法によって定められている下記の条件をクリアする必要があります。
【有給休暇がもらえる条件】
- 雇用された日から継続して6ヶ月間勤務していること
- すべての労働日の8割以上出勤していること
また、契約社員や派遣社員も同じように条件を満たしていれば、有給休暇を取得可能です。その場合は、勤務先の保育園ではなく派遣会社から付与されます。
付与される有給休暇の日数は、前述したとおり、就業日数によって変わってきます。
週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働時間が4日以下の場合は、もらえる日数が減るため、注意しましょう。
また、1年目の保育士の場合、基本的には入職して6ヶ月目以降に有給休暇をもらうことができますが、保育園によっては入職後すぐに付与されることも。園によってルールが異なるため、事前に雇用契約書を確認しておくのがおすすめです。
参考: 厚生労働省 「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
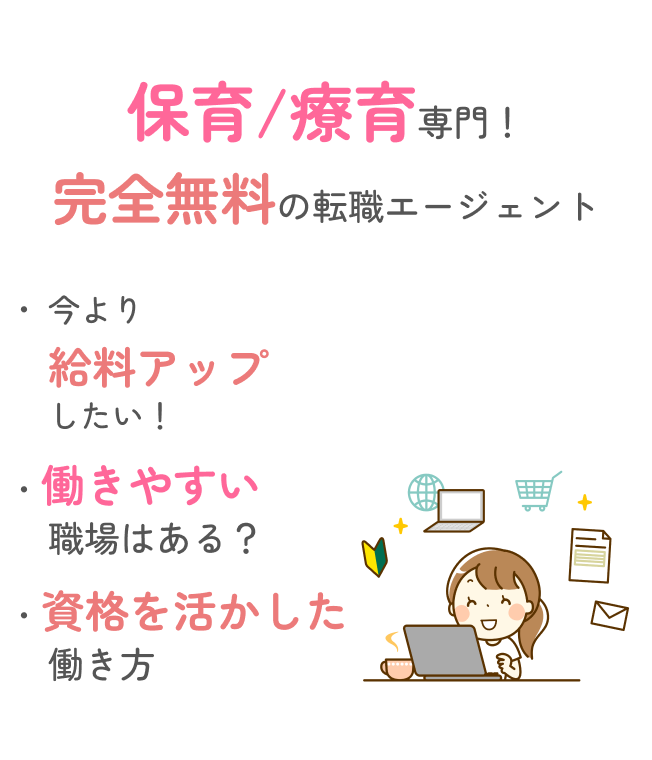

有給休暇がもらえない場合
繰り返しになりますが、有給休暇は条件を満たす労働者であれば取得できます。
労働基準法に基づく権利なので、条件を満たしているにも関わらず、有給休暇がもらえない場合は、「法人のご担当者」にご相談しましょう。もしかしたら行き違いなどがあるかもしれません。また、それでも改善されない場合は「労働基準監督署」に聞いてみるのも一つの手です。
労働基準監督署は公的機関なので、無料で相談が可能です。
明らかに労働基準法違反があると認められれば、職場へ改善指導や是正勧告をしてもらえる可能性があります。
そのため、有給休暇の件は法人の詳しい部署やどうしもで話を聞いてくれない場合は公共の窓口で聞いてみましょう。
参考:厚生労働省労働基準局 「労働基準監督年報」
有給休暇を消化できない場合はどうなるの?
「有給休暇をすべて消化できないのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。
2021年全国保育協議会の調査によると、保育園で働く正社員保育士の平均有給取得日数は、5~9日が44.2%、10~15日が42.5%という結果が出ています。
一方、全産業の労働者1人あたりの平均取得日数は10.9日です。
他業種と比べると、保育士の有給休暇取得日数は極端に少ないわけではありませんが、中にはもらった有給休暇を取得しきれていない可能性もあります。
前提として、有給休暇の有効期限は労働基準法によって2年と決められており、期限を過ぎてしまうと、消滅してしまう仕組みです。
付与されて2年以内の場合は、昨年の繰り越し分として取得できます。
せっかく付与された有給休暇の有効期限が切れてしまってはもったいないですね。
そのため、有給休暇が申請しやすい長期休暇にまとめて申請したり、忙しい時期を避けたタイミングに取得したりと、余裕をもって消化するのがおすすめです。
また、職場の退職日が決まっていて、期限内の有給休暇が余っている場合、基本的には消化できるでしょう。有給休暇は労働基準法によって定められている権利なので、基本的に保育園側が有給休暇の申請を拒否することはできません。
ただし、時期変更権*によって、保育園側が取得する時期の変更を促すことはできます。
*時期変更権とは
労働者が希望する日に年次有給休暇を与えることで、事業の正常な運営が妨げられる場合は、時期を変更できる権利が認められています。たとえば、同じ日に多くの保育士が休み希望を出して園の運営ができなくなる等の場合が考えられます。
参考: 全国保育協議会「全国保育協議会会員の実態調査2021報告書」
参考: 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況 」
参考: 厚生労働省 「年次有給休暇の付与日数は、法律で決まっています」
有給休暇を取らなければいけない日数

2019年4月より、事業者は労働省に対して、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が義務付けられました。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者で、1年以内に5日以上取得しなくてはなりません。
また、有給休暇を取得するタイミングは、労働者の意見を尊重して決めると定められているため、以前よりも希望にあわせて有給休暇がとれる場合もあります。
なお、正社員以外のパートやアルバイトも対象となるので、自分が付与される有休休暇がどれくらいなのか、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。
参考: 厚生労働省 「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」
参考: 厚生労働省 「年次有給休暇の付与日数は、法律で決まっています」
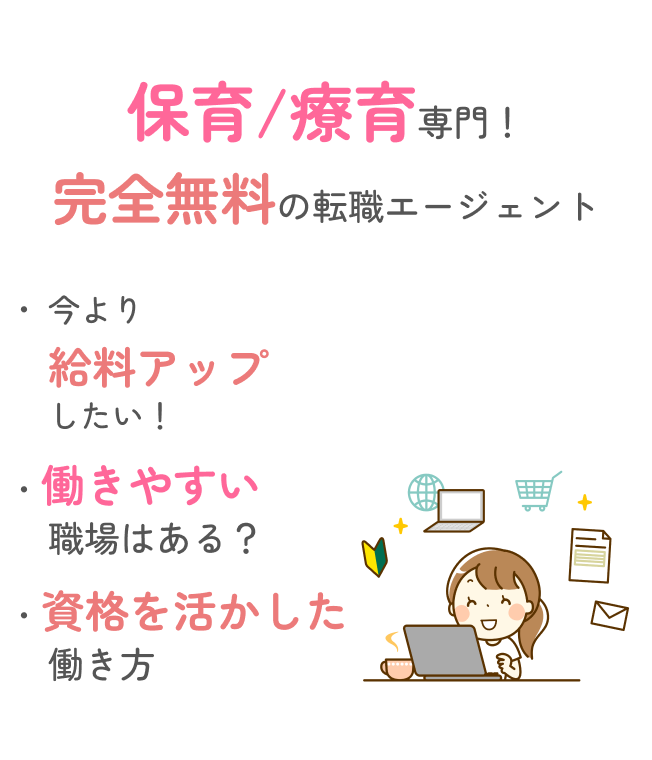

有給休暇が取れない場合の対策をご紹介
有給休暇がなかなか取れない場合は、下記の方法を試してみるとよいでしょう。
複数回に分けて取る
まとめて取るのが難しい場合は、複数回に分けて取るのがおすすめです。
園によっては、長期間休んでしまうと、職員の人手が足りなくなる可能性もあります。
そのため、1度に多くの日数を休むのではなく、1~2日程度の有給を分けて取得するのがおすすめです。
もし、まとめて有給休暇を取りたい場合は、一般的な長期休み等で登園する子どもが少ない時期に合わせて取るのがよいでしょう。
お盆休みや年末年始の時期は、保護者の方も休みの場合が多く、預かる子どもの人数が少ない分、長めのお休みも取りやすいかもしれません。
時期を考慮する
時期を考慮することで、有給休暇がとりやすい可能性があります。
保育園は、年度始めや年度末が忙しくなるタイミングがあります。
ほかにも運動会や発表会など大きな行事がある時期は、有給取得が難しいかもしれません。
また、冬は感染症が流行る時期なので、体調不良で職員の人手が足りなくなる可能性も。
そのため、上記のような時期を避ければ、少しでも有給休暇がとりやすくなるでしょう。
年度始めや年度末は、どの保育園も共通して忙しくなりますが、イベントの有無や開催時期は園によって異なります。
有給休暇が取りやすい園へ転職する
保育士不足などで有給休暇が取りづらい、もしくは取れない園で働いている場合は、有給休暇が取りやすい園へ転職するのも1つの手です。
最近は、保育士の働きやすさを重視している保育園も少なくありません。
同じ職場で保育士として長く働き続けるためには、休みの取りやすさも大切なポイントです。
求人サイトや、園のホームぺージを確認して、有給の取りやすい保育園をチェックしてみるのがおすすめです。
なお、有給休暇が取りやすいかどうかは、確認しづらいポイントなので転職エージェントなどを利用して相談してみるのもよいでしょう。
スムーズな有給休暇の取り方(ポイント)
スムーズに有給休暇を取るためには、下記のポイントを意識するのがおすすめです。
早めに相談する
有給休暇を取る場合は、主任や周りの保育士へ早めに相談するのがおすすめです。
事前に予定が決まっていれば、シフト調整や連携もスムーズにいくため、保育園に迷惑をかけずに済むでしょう。
自分の希望するタイミングに気兼ねなく有給休暇をとるためにも、主任や同じクラスの保育士へ早めに相談してみましょう。
日程のこだわりがなければ、希望日を複数提示するのも1つです。
有給候補日が複数あれば、保育園側がシフト調整しやすくスムーズに有給休暇をとれるでしょう。
引継ぎをしっかりおこなう
有給休暇を取る場合は、周りの保育士にしっかり引継ぎをおこないましょう。
休んでいる間は、代わりの保育士が業務をフォローするため、業務内容や子どもについての情報を細かく共有しておくのが大切です。
漏れがないように、メモにまとめておくと引継ぎがスムーズになります。
体調不良で有給を取りたい場合は速やかに連絡する
急遽、体調不良などで有給休暇をとる場合もあるでしょう。
その場合は、できるだけ早めに電話連絡を入れるのがベストです。
保育士はシフトで勤務していることがほとんどです。
抜けたシフトを代わりの誰かが補う手配をする必要がでてきます。
園の為にも早めに連絡を取って、体制を作る時間を確保できるよう早めの連絡を心掛けましょう。
また保育士の仕事は体力勝負で、健康管理が大切です。
体調が不安定な中で保育をすると、子どもたちの事故やケガにつながるリスクもあります。
インフルエンザや、新型コロナウィルスのような感染症にかかる可能性もあるため、無理をして出勤するのは望ましくありません。
普段からの体調管理こそ、保育士にとって大事な仕事の一つだと考えておきたいですね。
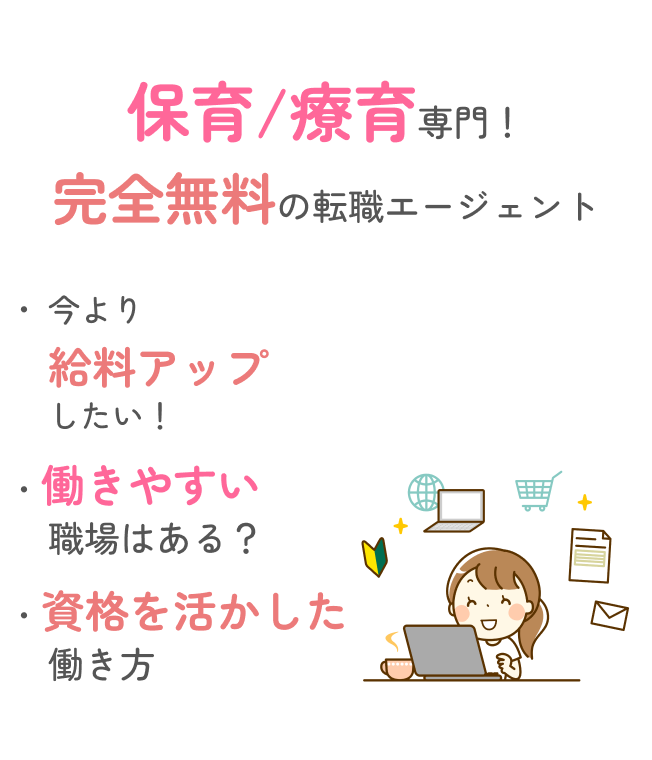

有給休暇が取りやすい園の特徴とは?

続いては、有給休暇が取りやすい保育園の特徴を5つ紹介します。
休みがとりやすい園へ転職を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
保育士が充足している園
保育士の人数が充分な保育園は、有給休暇が取得しやすい傾向にあります。反対に最低限の人数で運営している場合は、休みがとりづらい可能性があると言えるでしょう。
多めに保育士を配置している保育園は、保育士が休んでしまってもシフトが回るように体制を整えやすい傾向があります。
業務効率化を図っている園
従来、保護者へのお知らせや、指導計画は紙ベースで管理している保育園がほとんどでした。
しかし近年は、保育士の業務負担を解消するために、ICTシステムを導入している保育園も増えています。国も補助金制度を設けて、ICTシステムの導入を後押ししています。
保育士1人ひとりの業務量が減れば、仕事が終わらなくて休みが取れないということもなくなり、有給休暇もとりやすくなるでしょう。
比較的行事が少ない園
行事を少なくして、普段の保育に力を入れている保育園も休みがとりやすい傾向にあるといえるでしょう。
一方、行事が多い保育園は、保育士の業務量が多くなりやすく、有給休暇もとりづらい可能性があります。
小規模保育や家庭保育に力を入れている保育園は、比較的行事やイベントごとが少ないため、転職活動で求人をチェックしてみるのもおすすめです。
有給休暇取得率が高い園
保育士の人手不足を解消するために、近年はワークライフバランスに力を入れている保育園もあります。
園によっては、求人ページやホームぺージに詳しく情報を掲載している場合もあるため、転職を検討している方は下記のような情報がないかチェックしてみるのもよいでしょう。
- 平均取得日数
- 職員の取得率
過去の実績があると安心して転職ができるのではないでしょうか。
運営母体が大きい
一部上場企業など大きな株式会社が運営している保育園は、有給休暇がとれやすいといえます。
特に上場企業は、コンプライアンスを順守している傾向にあり、決められた日数の有給がしっかり取得できるか管理している場合もあります。
また、母体が複数の保育園を運営している場合、系列園の中で保育士のシフトを調整することも考えられるでしょう。
保育士の有給休暇まとめ
保育士の有給休暇について、日数やもらえる条件、取れない場合の対策などをご紹介しました。
有給休暇は条件を満たしていれば、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員にも付与されます。
保育士は、仕事が忙しく、人手不足というイメージから、「有給消化ができないのでは?」「辞める時にも消化できないのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、有給休暇は労働基準法で守られている大切な権利です。
2019年からは5日以上の取得が義務化され、有給休暇が取りやすくなりました。
もし、今働いている保育園が有給を全く取らせて貰えない園であれば、転職を検討するのも1つの手です。
有給取得率が高い保育園や、働きやすい環境を整えている保育園へ転職すれば、今の悩みが改善される可能性もあるでしょう。
もし転職を検討する場合は、保育士専門の転職エージェントである保育士人材バンクをご利用されてみてはいかがでしょうか。
離職率が低めの保育園、残業なし・持ち帰りなしの保育園など、自分が大事にしたいと思う条件をお伺いしながらあなたにマッチした職場を無料でご紹介いたします。
また、働きながらの転職活動が難しい方に向けて、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策などもしっかりサポートさせていただきます。
「今より働きやすい保育園で働きたい」、「保育士の資格を活かして転職したい」など、悩んでいる保育士さんはぜひお気軽にご相談ください。

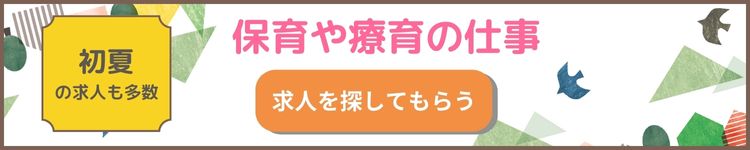
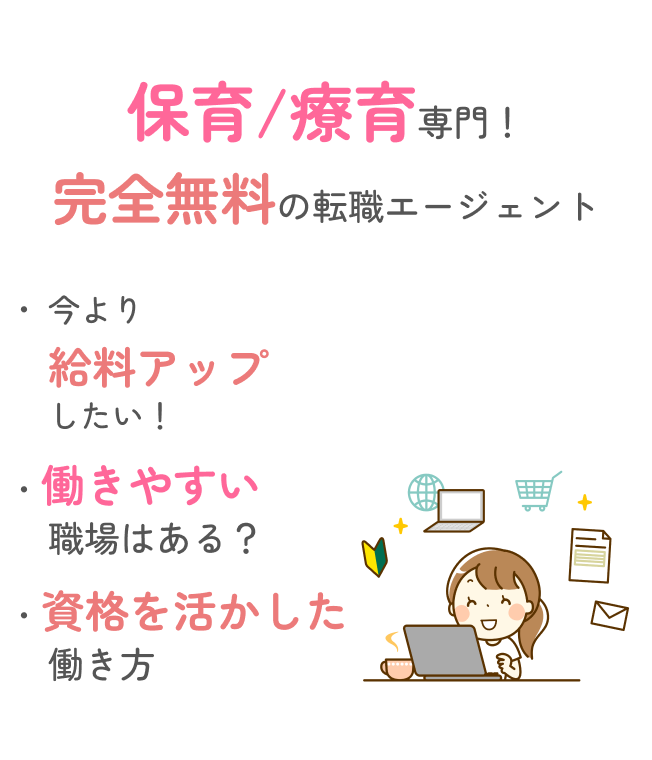


?保育園と幼稚園で違いはある?【保育士人材バンク】-scaled.jpg)