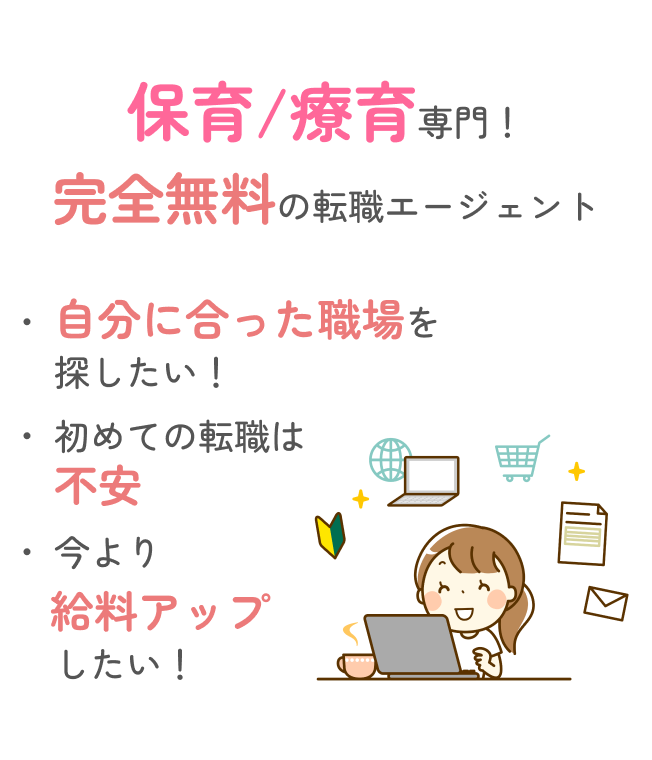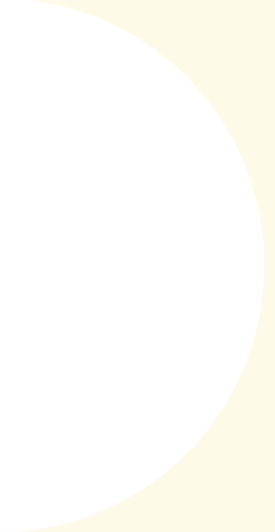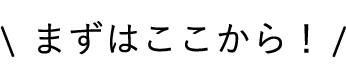保育士試験の実技試験は、筆記試験合格後に行われます。
音楽、造形、言語の3分野のうち、2つの分野を選んで両分野とも合格すれば、晴れて保育士資格が取得できます。
本記事では保育士の実技試験について、詳しく解説します。
保育士試験の実技とは
保育士試験は、筆記試験と実技試験の二段階で構成されており、筆記試験の9科目全てで満点の6割以上を取ると、実技試験へと進めます。
保育士試験は、年に二度(前期、後期)行われています。前期と後期のどちらも筆記試験が2日間にわたって行われ筆記試験の合格者を経て実技試験が行われます。
筆記試験同様、実技試験も再試験が可能で、もし落ちてしまっても筆記試験の合格科目の有効期限内であれば、何度でも受け直すことができます。
試験日程や会場、試験科目など最新の保育士試験に関するくわしい情報については「全国保育士養成協議会」公式HPでご確認ください。
実技試験は3分野から選べる
保育士の実技試験は、以下3分野の中から2分野を選んで受験します。
- 音楽
- 造形
- 言語
分野を選ぶのは、保育士試験の申請をするときで筆記試験より前となります。一度申請すると変更はできないので、保育士試験を申し込む際に判断しましょう。
実技試験は50点満点で、筆記試験同様、6割(30点)以上の評価で合格となります。
実技試験の流れ
筆記試験に受かったら、「実技試験受験票(筆記試験結果)」が届きます。
受験票には、ガイダンス開始時刻と試験会場、実技試験の選択分野などが載っていまので、ガイダンス開始時刻までに試験会場に集合します。ただし、電車遅延など不測の事態も考慮して余裕を持って会場に到着をするようにしましょう。
実技試験の音楽
ここからは、実技試験3分野のくわしい内容について解説します。
実技試験の「音楽」では、保育を行う子どもに聴かせることを想定した、楽器の弾き歌いを行います。弾き歌いに使える楽器はピアノかギターで、ピアノを弾く場合は会場に設置されたピアノを使い、ギターは持参する必要があります。
ピアノ、ギターいずれの場合でも一般社団法人全国保育士養成協議会「実技試験について」をよく読み持参する物や注意点を確認しておきましょう。
また、音楽の試験では、楽器による伴奏と歌唱の両方を行いますので、伴奏だけ、歌だけの演奏ではありません。
課題曲の単旋律の楽譜は事前の課題と共に示されるので、それを確認して練習を行いましょう。
令和7年の課題曲
音楽の試験の課題曲は2曲あり、その両方を演奏します。課題曲は事前に知らされているので、事前の練習が可能です。
令和7年後期の課題曲は、以下2曲です。
- 『ハッピー・バースデー・トゥ・ユー』(作詞・作曲:Mildred J. Hill and Patty Smith Hill)
- 『証城寺の狸囃子』(作詞:野口雨情 作曲:中山晋平)
引用:一般社団法人全国保育士養成協議会「実技試験(後期)概要」
基本的には、課題曲以外を練習する必要はありませんが、参考までに過去3年の課題曲を紹介します。
- 令和6年
『夕焼け小焼け』(作詞:中村雨紅 作曲:草川信)
『いるかはザンブラコ』(作詞:東龍男 作曲:若松正司)
- 令和5年
『幸せなら手をたたこう』(作詞:木村利人 アメリカ民謡)
『やぎさんゆうびん』(作詞:まど・みちお 作曲:團伊玖磨) - 令和4年
『ことりのうた』作詞:与田準一 作曲:芥川也寸志
『びわ』作詞:まど・みちお 作曲:磯部俶
例年、子どもに身近な童謡を中心に出題されていますね。
実技試験の造形

実技試験の「造形」では、指定された保育のある一場面を、絵画で表現します。
表現に関する問題文と条件を試験当日に提示されます。指定された一場面を条件を満たしたうえで表現していきます。試験時間は45分です。
当日は以下の持ち物を準備します。
- 鉛筆またはシャープペンシル(HB~2B)
- 色鉛筆(12~24色程度)
- 消しゴム
- 腕時計
特に「色鉛筆」は一般社団法人全国保育士養成協議会が出している「実技試験について」を確認しておきましょう。
引用:一般社団法人全国保育士養成協議会「実技試験(後期)概要」
また、解答用紙の大きさはA4判、絵を描く枠の大きさは縦横19㎝で、紙の種類は当日に提示されます。
指定された保育の情景がイメージできるような表現を目指しましょう。当日に向けて、試験本番と同じ大きさの紙と、色鉛筆などの道具を用意して、制限時間と同じ45分で練習するとよいでしょう。
実技試験の言語
実技試験の「言語」は、子どもたちに向けたお話を想定して行う試験です。過去の問題を見ると、3歳児が15人ほど目の前にいるというイメージで、3分間のお話をします。
絵本や台本、人形などの使用は禁止されているので、一般的なあらすじから自分なりにお話の流れを把握した上で、暗記する必要があります。
子どもに理解できる言葉で、その場にいる全員に聞こえるようにしっかり声を出して話しましょう。
令和7年の言語試験の課題は、以下3つのお話です。
- 1.「ももたろう」(日本の昔話)
- 2.「おむすびころりん」(日本の昔話)
- 3.「3びきのこぶた」(イギリスの昔話)
3つのうち、どの課題について話すかは試験当日の入出後に指定されます。指定された課題以外を行った場合は、採点の対象外となりますので、1~3のどの課題でも話せるように練習しておきましょう。
保育士試験 実技のまとめ
保育士試験は、筆記試験と実技試験の二段階で構成されており、筆記試験で全ての科目に合格したら、実技試験へと進めます。
保育士試験は年に二度行われており、どちらの回でもまず筆記試験が2日間にわたって行われ、筆記試験の合格者発表を経て、実技試験が行われます。
実技試験には以下3つの分野があり、このうち2分野を選んで受験します。
- 音楽
- 造形
- 言語
分野を選ぶのは、保育士試験の受験申請のタイミングですので慎重に決めましょう。
どの分野の試験も、事前の準備が重要です。試験の内容を一般社団法人全国保育士養成協議会が出している「実技試験について」を漏れなく確認し、十分に練習をして試験本番に備えましょう。