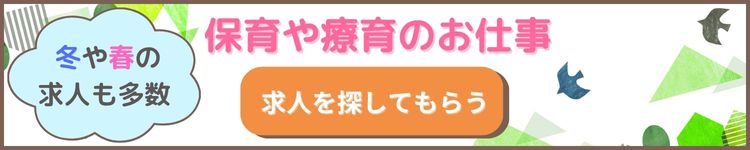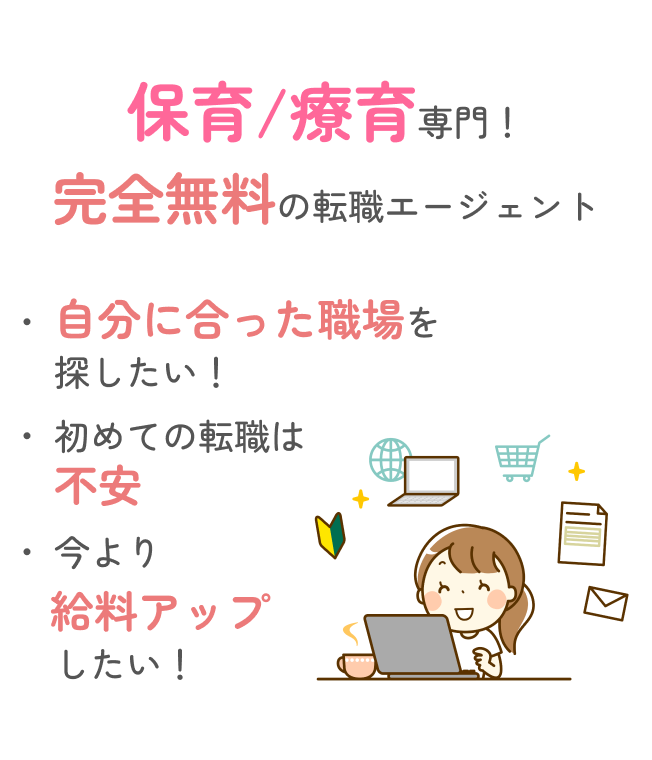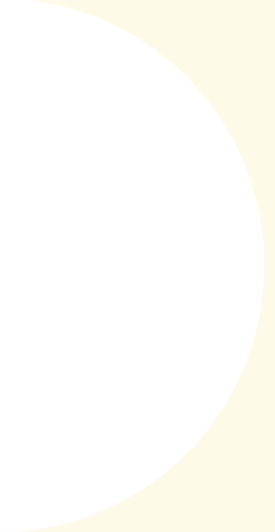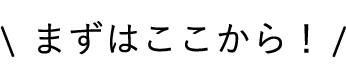保育士は子どもの成長を支える国家資格であり、社会人から目指す方も増えています。
とはいえ「どうやって資格をとるの?」「働きながらでも大丈夫?」と疑問に思う方も少なくありません。
本記事では、保育士資格の基本的な取り方から、働きながらでも取得を目指せる方法までわかりやすく解説します。
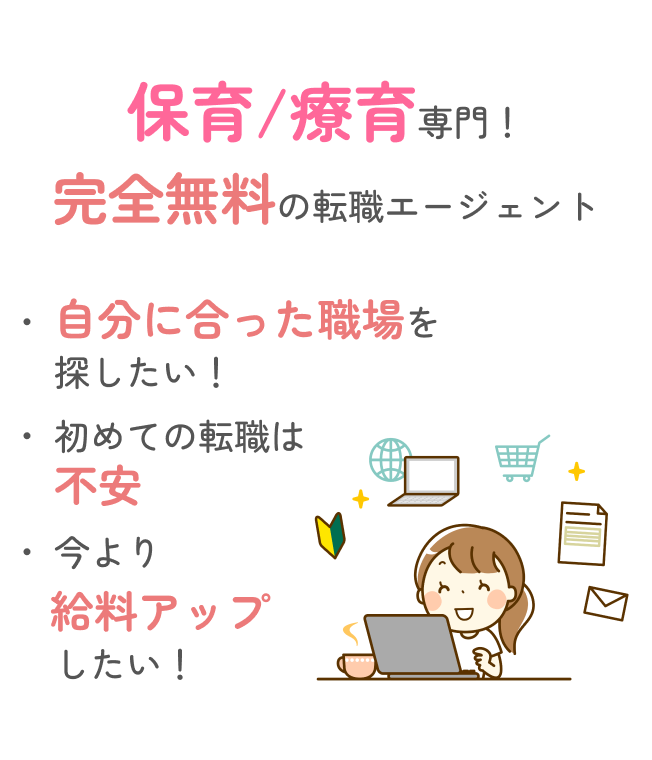

保育士とは
保育士とは、子どもの健やかな成長や発達を支える国家資格の専門職です。
保育園や認定こども園、児童福祉施設などで、0歳から小学校就学前までの子どもを対象に保育や生活支援をおこないます。
具体的な定義は、児童福祉法第18条の4において次のように定められています。
“保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。”
つまり、保育士は単に子どもの世話をするだけでなく、専門的な知識と技術を基盤に、子どもへの保育と保護者への支援をおこなう役割があると明確に示されています。
また、家庭との連携を図りながら子育て相談に応じるなど、地域や家庭を支える存在としての役割も担っています。
共働き世代の増加や待機児童問題など社会的背景を踏まえると、保育士は今後もますます重要性を増す職業だといえるでしょう。
参考:全国保育士養成協議会「保育士試験とは」
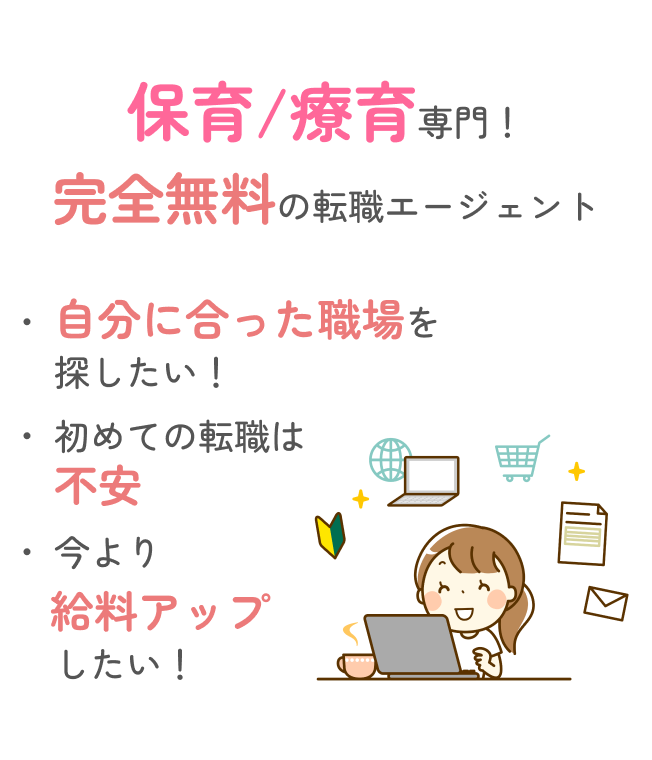

保育士資格の取り方
保育士資格を取得する方法は大きく分けて「保育士養成課程を修了する」と「保育士試験に合格する」の2つがあります。
ここでは、それぞれの特徴について詳しく解説します。
養成課程を修了して取得する方法
大学・短大・専門学校などに設置されている保育士養成課程を卒業すると、保育士試験を受けずに資格を取得できます。
カリキュラムには座学にくわえ、保育園や児童福祉施設での実習も含まれており、現場で役立つ知識や技術を体系的に学べるのが特徴です。
もっとも王道のルートであり、卒業と同時に資格を得られるのがメリットです。
保育士試験に合格して取得する方法
学歴や実務試験など一定の条件を満たした人は、年2回実施される保育士試験を受験できます。
筆記試験と実技試験の両方に合格することで資格を取得でき、社会人から保育士を目指す人や、他分野からの転職を希望する人が多く選ぶルートです。
独学や通信講座を活用できるため、働きながらでも挑戦しやすい方法といえます。
状況別取得方法
保育士資格を取るための方法は、学歴やこれまでの経歴によって異なります。ここでは、社会人・大卒者・高卒者・中卒者のケースに分けて取得ルートをご紹介します。
社会人の場合
社会人から保育士を目指す場合は、保育士試験を受験して資格を取得するルートが一般的です。すでに大学や短大を卒業していれば受験資格を満たしているため、筆記試験と実技試験に合格すれば資格を取得できます。
働きながら勉強を進めるのは大変ですが、独学や通信講座を活用して効率的に学習する人が多いのが特徴です。とくに通信講座は、自分のペースで学べることにくわえ、添削や質問サポートが受けられるため、限られた時間で学習したい社会人に向いています。
また、科目合格制度があるため、一度に9科目すべてを合格する必要はありません。1度合格した筆記試験は、3年間は有効とされているため、計画的に受験することも可能です。仕事や家庭と両立しながらでも挑戦しやすく、社会人にとってチャレンジしやすい国家資格といえるでしょう。
参考:全国保育士養成協議会「免除制度について」
大卒の場合
大学を卒業している方は、保育士試験を受験するのが資格取得への基本的なルートとなります。大卒者は受験資格を満たしているため、筆記試験と実技試験に合格すれば保育士資格を取得可能です。
大学で保育や教育に関する科目を履修していた場合には、一部の科目が免除されるケースもあります。そのため、過去の履修内容や単位を確認しておくとよいでしょう。
また、前述したとおり、現在は働きながら資格取得を目指す社会人も多いため、通信講座や夜間スクールを利用して学習を進める方法が人気です。
大卒の方は受験資格のハードルをすでにクリアしているため、あとは効率よく学習を積み重ねて合格を目指すことが重要になります。
高卒の場合
高校卒業者は、すぐに保育士試験を受けられるわけではありません。
条件として、児童福祉施設などで一定期間の実務経験を積む必要があります。具体的には、2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験があれば受験資格が認められます。
もう1つのルートとして、短大や専門学校などの保育士養成課程に進学し、卒業と同時に資格を取得する方法もあります。実習や専門科目を体系的に学べるため、実践力をつけながら資格を取りたい方に向いています。
中卒の場合
中学校卒業者は、現時点でそのまま保育士試験を受験することはできません。まずは高校卒業資格を取得する(通信制高校や高認試験など)ことが必要です。
その後、短大や専門学校で養成課程を修了する、もしくは実務経験を積んで保育士試験を受験するという流れになります。
社会人からでもルートを踏めば資格取得は可能なので、まずは学歴要件を満たすところから始めることが大切です。
参考:全国保育士養成協議会「受験資格詳細」
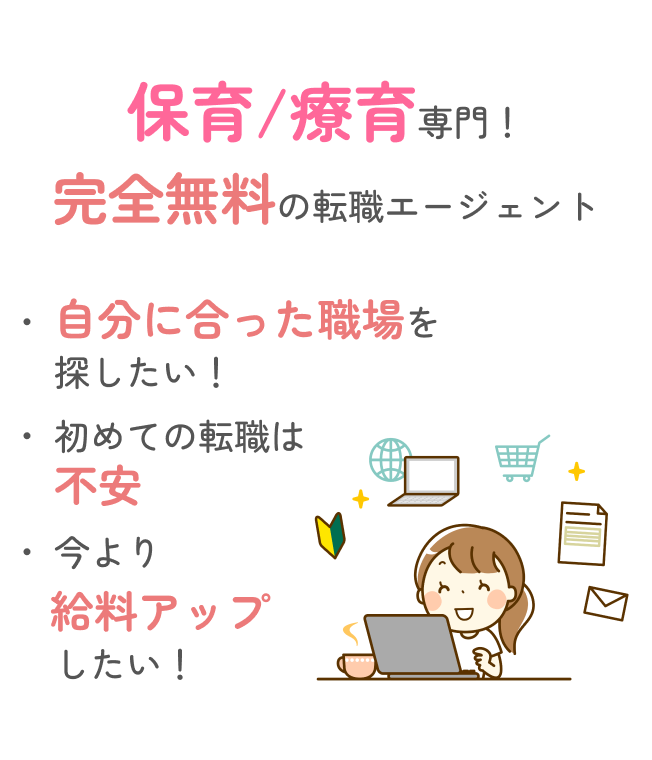

保育士になるメリット

保育士は国家資格であり、子どもの成長を支える専門職として多くのやりがいがあります。資格を取ることで、安定した就職先が見つかりやすくなり、キャリアの可能性も広がるのは嬉しい魅力です。
ここでは、保育士になることで得られるメリットを5つご紹介します。
国家資格による安定性
保育士は国家資格であるため、全国どこでも働ける強みがあります。
保育園や認定こども園はもちろん、児童養護施設や障がい児施設など幅広い分野で必要とされており、就職や再就職に強いのが特徴です。
結婚や出産、転居などライフスタイルの変化があっても働き口を見つけやすく、一度資格を取得すれば一生ものの武器となります。
資格を持たない仕事と比べても雇用が安定しているため、安心して長く働き続けられる点が大きなメリットです。
社会的ニーズが高い
近年は共働き世帯の増加や待機児童問題の影響で、保育士の需要は全国的に高まっています。今後も人材が必要とされる状況が続くと予測されています。
保育士資格を持っていれば、求人の多さから勤務地や勤務形態を選びやすく、自分に合った働き方を実現しやすいのも魅力です。
「資格があるのに働き口がない」という心配が少なく、キャリアの安心感につながります。
子どもの成長に関われるやりがい
保育士の最大のやりがいは、子どもの成長を間近で見守れることです。子どもが「初めて歩いた」「言葉を話した」「友達と仲良く遊べた」そんな瞬間を共に喜べるのは保育士ならではの魅力です。
日々の保育を通して「自分が関わったことで子どもが少しずつ成長している」と実感できることは、大きなモチベーションになります。
子どもや保護者からの「ありがとう」の言葉も、仕事の励みになるでしょう!
キャリアの幅が広がる
保育士資格は、働く場所やキャリアの選択肢を広げてくれます。
保育園や認定こども園にとどまらず、企業内保育や病院内保育、学童保育や児童福祉施設など多岐にわたる現場で活躍できます。
さらに経験を積めば、主任保育士や園長といった管理職を目指す道もありますし、子育て支援センターや行政関連の仕事に進むことも可能です。
将来的に独立して小規模保育施設を立ち上げるケースもあり、キャリア形成の幅が広いのも大きな魅力です。
ライフスタイルに合わせて働ける柔軟性
保育士の大きな魅力のひとつは、働き方の選択肢が豊富なことです。
正社員として安定して働くのはもちろん、パートや派遣、短時間勤務といった形でライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
たとえば、子育てや家庭と両立したい方は、午前中のみのシフトや週3日勤務を選ぶこともできます。また、フルタイムでしっかりキャリアを積みたい方は、正社員として経験を重ねながら主任保育士や園長といったキャリアアップを目指す道もあります。
さらに、近年は企業内保育や院内保育など多様な職場環境が増えており、自分の生活スタイルに合った勤務先を選びやすくなっています。
資格を持っていれば働き方の幅が広がり、ライフステージの変化に合わせて柔軟にキャリアを築けるのも保育士ならではの強みです。
独学でも取得できるの?
保育士資格は独学でも取得を目指すことが可能です。とくに筆記試験はマークシート方式で知識問題が中心のため、自宅学習でも対策がしやすい試験です。
ただし、9科目をバランスよく学ぶ必要があるため、計画性と継続力が重要になります。ここでは、独学で挑戦する際のポイントを整理しました。
独学で挑戦するメリット
独学の最大のメリットは、費用を抑えられることです。市販のテキストや過去問集を活用すれば、数千円~数万円程度で学習を進められます。
また、自分のペースで学習できる自由度も魅力です。仕事や家事の合間に取り組んだり、得意科目を短期間で仕上げるなど、柔軟にスケジュールを調整できます。
さらに、保育士試験には科目合格制度があり、1度に全ての科目を合格する必要はありません。数年をかけて段階的に合格を積み重ねられるため、独学での学習方法とも相性が良い仕組みといえます。
独学のデメリットや注意点
一方で、独学はモチベーションの維持が難しいという課題があります。周囲に一緒に勉強する仲間がいない場合、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
また、最新情報の入手が遅れるリスクもあります。試験制度や出題傾向は年度ごとに変わることがあるため、実技試験対策は独学だと限界がある場合も。
ピアノ演奏や読み聞かせは実際に声や音を出す練習が必要で、自己流では評価基準に合っているか不安が残りやすい点に注意しましょう。
独学で合格するための勉強法
独学で合格を目指すなら、過去問演習を中心に学習することがカギです。繰り返し解くことで出題傾向を把握し、効率よく知識を定着させられます。
また、学習スケジュールを細かく立てることも重要です。1日30分でもよいので継続的に取り組み、進捗を見える化するとモチベーション維持につながります。
実技試験の準備については、ピアノは課題曲を簡単にアレンジして練習したり、読み聞かせは自分の声を録音して確認するなど、工夫次第で独学でも対応可能です。
独学が不安な場合のサポート活用法
「独学だけでは不安・・・」という方は、通信講座やスクールを部分的に利用する方法もあります。模擬試験や添削課題を取り入れることで、独学では得にくい客観的なフィードバックが得られます。
また、オンラインコミュニティやSNSで学習仲間を見つけるのも効果的です。進捗を共有し合うことで、挫折しにくくなります。
独学を基本としながらも、必要に応じてサポートを取り入れることで、安心して合格を目指すことができるでしょう。
保育士資格の取り方まとめ
保育士資格を取得する方法は、養成課程を修了するルートと、保育士試験に合格するルートの2つがあります。
社会人や異業種からの転職を考えている方でも、学歴や実務経験に応じて挑戦できる道が用意されているため、誰でも目指すことが可能です。独学や通信講座を活用しながら、計画的に学習を進めることが合格への近道となります。
そして、資格を取った後には、自分に合った働き方を考えることが大切です。保育士人材バンクでは、試験の解答速報や学習に役立つ情報の発信だけでなく、資格取得後の就職支援までトータルでサポートしています。
安心して学び、保育士としてキャリアを築いていけるよう、ぜひ活用してみてください!