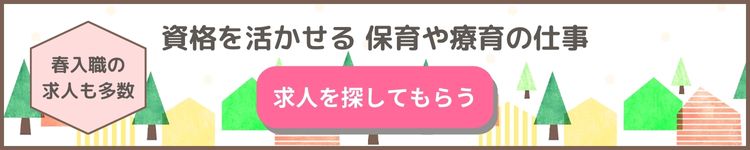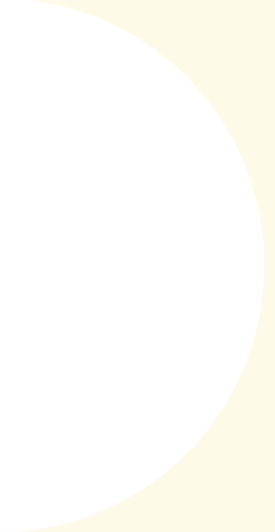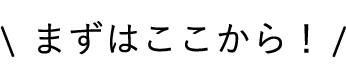保育士として働いているうちに、「障がいを持つ子どもへの関わり方をもっと学びたい!」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介する児童発達支援とは、障がいを持つ子どもと保護者をサポートする福祉サービスのひとつです。
今回は、児童発達支援の持つ役割や具体的な仕事内容を解説します。障がい児と関わる仕事ならではのやりがいや魅力を知り、実際に働くイメージを膨らませてみてくださいね。
児童発達支援とは?
児童発達支援とは、就学前の子どもが福祉サービスを受けるための施設です。これまで存在していた子どもの福祉サービスは障がいの種類ごとに分けられていましたが、2012年の児童福祉法改正にともない通所・入所の利用形態別で一元化され、「児童発達支援」が定められました。
厚生労働省が発表した「児童発達支援ガイドライン」には、児童発達支援の役割について以下のように定めています。
「児童発達支援は、児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に基づき障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである。」
引用)厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」
具体的には、身体障がいや知的障がい、発達障がいなどを持つ子どもや療育が必要と認められた子どもが対象となります。通所するうえで障がい者手帳は必ずしも必須ではなく、児童相談所や市町村の保健センター、医師などが、「療育の必要性」を感じた場合にも利用することができます。
児童発達支援の種類
児童発達支援には、児童福祉施設に定義される「児童発達支援センター」と、それ以外の「児童発達支援事業」の2種類があります。
- 児童発達支援センター
通所する子どもに療育を提供する以外にも、子どもが通う保育施設をはじめ、地域の関係機関とも連携する役割を持つ。専門性を活かし、子どもと家族がその地域で暮らしやすいように働きかける。
- 児童発達支援事業
通所する子どもの発達支援や家族への相談業務をメインに行う施設。日常生活での困りごとや発達に関する不安に合わせて、適切なカリキュラムを作成し、療育を提供する。
児童発達支援センターは、地域の中枢機関としてさまざまな役割を担うため、自治体や社会福祉法人など、比較的規模の大きい運営元であるケースが多く見られます。一方、児童発達支援事業は都道府県の指定を受けた事業所が運営でき、小規模なものから大きな事業所まで幅広いのが特徴です。
放課後等デイサービスとの違い
児童福祉法には、放課後等デイサービスという施設も定められていますが、児童発達支援事業とは対象年齢や役割が異なります。
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援事業 | |
| 対象年齢 | 6~18歳までの就学児 ※自治体に必要性が認められた場合は20歳まで | 0~6歳までの未就学児 |
| 施設の 役割 | ・対人関係や身辺自立のほかに、学習や就労に関する支援も行う ・社会と交流する機会を持ち、地域のなかで暮らすために必要なスキル習得を支援する | ・身の回りや食事、身体機能の向上など、日常生活における自立を目指す支援を行う ・集団生活で必要な社会性やコミュニケーションの成長を促す |
参考)「児童福祉法 第六条の二の二」
対象年齢や具体的な活動内容は違っていても、どちらも利用者の障がいや特性を理解し、適切なプログラムを提供する施設です。子どもと保護者の不安や生きにくさが解消できるように、療育や関係機関との連携を通してアプローチしていきます。
児童発達支援の一日の流れ

児童発達支援の施設や事業所は、子どもの支援計画に基づいて活動を決めています。施設や事業所によっては親子一緒に行う療育があったり、通所回数を選べる場合があったりと実際の運営形態はさまざまです。
今回は、とある児童発達支援施設のスケジュールを例に挙げてみましょう。
<流れ>
| 時間 | 全体の流れ | 保育士の動き |
| 8:30~ | 出勤施設内の清掃打ち合わせ | |
| 9:00~ | 子ども(保護者)来所 | お出迎え健康状態のチェック療育の準備 |
| 9:30~ | 療育 | 計画に沿った療育プログラムの提供様子の記録 |
| 12:00~ | 昼食 | 食事のサポート・見守り片付け |
| 13:00~ | 自由時間 | 事故予防見守り |
| 14:00~ | 保護者のお迎え見送り | 子どもの様子の報告相談対応 |
| 15:00~ | 事務作業 | 療育の記録職員間のミーティング翌日の療育準備 |
| 17:00~ | 清掃 | |
| 17:30~ | 退勤 |
上記の例は一日を通して同じ子どもと保護者に対応するスケジュールですが、午前と午後で別の子どもを受け入れている事業所もあります。施設ごとに活動内容や保育士の仕事内容の特色があるので、転職活動の際は求人の詳細や施設のホームページなどで具体的な運営状況の確認をおすすめです。


児童発達支援の仕事内容
児童発達支援は施設によって仕事内容も異なりますが、子どもと保護者に寄り添い、障がいや生活で困っていることに対して支援する点は同じです。具体的には、次のような仕事を担っています。
個別・集団療育
児童発達支援での療育は、大まかに「個別療育」と「集団療育」に分けられます。
個別療育では、保護者の要望や子どもの特性をくみ取って個別に課題を提供するのが特徴です。理解、対人、言葉、感覚など、本人がとくに困っている部分は子ども一人ひとり異なります。個別療育なら、子どもの特性や成長に合わせた細かい工夫もできやすくなります。
集団療育は、年齢や障がいの特性で分けられた少人数のグループに対し療育を提供します。個々への丁寧な関わりに加えて、コミュニケーションの取り方や、社会性を学べるプログラムが多いのが特徴です。子ども同士が認識している空間で、褒められ認められる経験を育みます。
保護者支援
児童発達支援の仕事内容には、子どもだけでなく保護者対応も含まれます。保育士からは子どもの特性や具体的な関わり方を伝え、保護者からは家庭の様子を聞き取り、お互いに情報交換を行います。
障がい児の保護者のなかには、育てにくさや不安を感じている方も多く、発達の知識を持つ保育士を頼りにしているケースも多いでしょう。関わり方のアドバイスや、家族のニーズに合った関係機関への橋渡しも必要となります。
また、児童発達支援に通っていても、すべての保護者が子どもの障がいについて理解しているとは限らず、場合によっては子どもの特性に気づけるよう働きかけなくてはいけません。保護者の受け止めや伝え方を見極めながら、慎重に進める必要があります。
個別支援計画の作成
障がいの特性や興味・関心など、子どもの様子に適したアプローチを行うには、個別支援計画の作成が欠かせません。支援計画の作成は児童発達支援管理責任者の業務ですが、具体的な様子をより細かく知るため、そのほかの職員もミーティングに参加して精査するのが一般的です。
個別支援計画は保護者に確認してもらい、その後も決められた期間ごとに見直しを行います。保護者のニーズや子どもの成長に合わせて変化させていくため、日々の療育で丁寧に記録を残しておくことがとても大切です。
近年では、仕事のICT化も進んでおります。
児童の記録作成や請求業務など、仕事の効率化を行っている事業所もあります。
児童や保護者、職員と直接コミニケーションが取れる時間が増えることは嬉しいことですね。
参考:保育業界から児童発達支援事業所を開業!手厚いサポートでカイポケ導入もスムーズに
代表的な仕事以外にも、掃除や次の日の準備など多岐にわたる仕事を行います。
また、事業所によっても仕事内容が変わり、事前に見学などを通して把握することも一つの手でしょう。
児童発達支援で働く職種
児童発達支援で必要とする職種は、児童発達支援センターと児童発達支援事業で異なります。
| 児童発達支援センター | ・児童発達支援管理責任者:1人以上 ・児童指導員及び保育士:子ども4人につき1人以上 ・児童指導員:1人以上・保育士 1人以上 |
| 児童発達支援事業 | ・児童発達支援管理責任者:1人以上 ・児童指導員及び保育士:子ども10につき2人以上 ※うち半数以上は児童指導員又は保育士 |
参考)厚生労働省「障害児支援施策の概要」
児童発達支援が保育士を必要としている理由

児童発達支援を含む子どもの福祉サービスは、近年右肩上がりで施設数と利用者を伸ばしています。
<利用者数の推移>
| 平成24年度 | 令和元年度 | |
| 放課後等デイサービス | 54,819人 | 216,848人 |
| 児童発達支援 | 57,929人 | 122,441人 |
| その他サービスを含めた全体 | 116,309人 | 345,032人 |
参照)厚生労働省「児童発達支援・放課後等デイサービスの現状等について」
児童発達支援センターは子ども4人に対して1人の保育士、児童発達支援事業では子ども10人に対し2人以上の保育士の配置が必要です。児童福祉サービスの利用者が増えれば、そのぶん保育士も必要になるのも必然といえるでしょう。
施設数の増加とともに、すぐに保育士を確保できれば問題ありませんが、残念ながら保育業界では保育士不足の状況が続いています。以下は厚生労働省が調査した保育士資格を持つ方と実際に保育業界で働く保育士の人数の推移です。
<保育士の登録者数と従事者数の推移>
参照)厚生労働省「保育士の登録者数と従事者数の推移」
保育士になる方が増えていても、比例するように潜在保育士も増加しています。保育業界ではまだまだ保育士が必要とされており、それは利用者が年々増えている児童発達支援の職場でも同様です。
児童発達支援の現場で働くには、障がいの知識やスキルも求められます。新卒者はもちろん、保育経験のある方の転職者なら療育現場からも保育士資格をお持ちの方は大いに必要とされるでしょう。


保育士が児童発達支援で働くメリット
保育園やこども園をはじめ、保育士の働く職場にはさまざまな選択肢があります。そのなかでも、児童発達支援で働くメリットをお伝えします。
障がいや療育に関する知識と経験を学べる
支援を必要とする子どもたちと関わり、適切な療育を行うためには、障がいの知識や関わり方のスキルが必ず求められるでしょう。ですが、誰もがはじめは未経験から始まり、徐々に知識とスキルを身に付けていくので必要以上に怖れることはありません。
障がいを持つ子どもへの関わり方や発達について学びたい方であれば、実践しながら身に付けられる児童発達支援での経験は大きなスキルアップになります。
子ども一人ひとりと向き合える
保育園では、毎日の流れに加えて行事の練習や準備などを大勢の子どもたちに向けて行うため、時間や作業に追われてしまうこともしばしばあります。個別もしくは少人数で療育を行う児童発達支援では、少人数で子どもにじっくりと向き合いやすいのがメリットです。
子どもが興味を持っている活動を満足するまで提供したり、理解しやすいように絵を書いて伝えるなど、活動内容も子どもの特性に合わせやすいといえます。
児童発達支援で働く保育士のキャリアアップ例

児童発達支援で働いて得たスキルを活かすなら、以下のようなキャリアアップや転職が挙げられます。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスなら、就学後も長期にわたって子どもの成長を見守れます。保育園や児童発達支援では経験できない、生活に必要なスキル習得や学習支援などを身に付けられる点が魅力です。年齢にとらわれない、目の前の子どもの発達に合わせた療育に興味のある方は、ぜひこの先のキャリアアップのひとつとしてご検討ください。
児童発達支援管理責任者
児童発達支援の施設で働きながらキャリアアップを目指したい方は、児童発達支援管理者になる目標を掲げるのもおすすめです。児童発達支援の事業所には必ず1人は配置されるよう義務付けられ、個別計画の作成や評価、相談業務など幅広い業務をこなします。取得するまでのハードルが高いぶん保育士よりも高収入な場合が多く、将来性が期待できる職種です。
保育園や認定こども園の加配保育士
保育園やこども園には、支援が必要な子どもに寄り添う加配保育士がいます。保育士の養成学校や保育士試験で障がい児保育について学んでいても、実際の障がい児への関わり方に悩む保育士は少なくありません。障がいについての知識や高いスキルを持っている保育士は、保育園にとって心強い存在です。個別や小集団の療育で実際に行ってきたことを、集団生活で活かすチャンスとなります。
【2024年最新】加配保育士とは?やりがいや、役割・仕事内容をくわしくご紹介!
児童発達支援まとめ
児童発達支援は、障がいを持つ就学前の子どもと保護者が通う通所施設です。子どもに合わせた療育を行うのは大変さもありますが、児童発達支援で働く経験は保育士として大きなスキルアップにつながるでしょう。療育の知識や経験を持つ保育士は、保育園やこども園をはじめ、ほかの職場でも重宝されます。保育士としてさらに一歩成長したい方は、ぜひ療育を学べる児童発達支援も検討してみてくださいね。
保育士人材バンクでは、児童発達支援のお仕事や放課後等デイサービス、小規模保育園などの求人もご紹介しております。
「保育士資格を持っているけど、どんな求人があるかわからない」「自分にあった職場を探したい」という方は、是非保育士人材バンクにご相談をしてみてください。
ご自身にあった最適な求人をご紹介させていただきます。