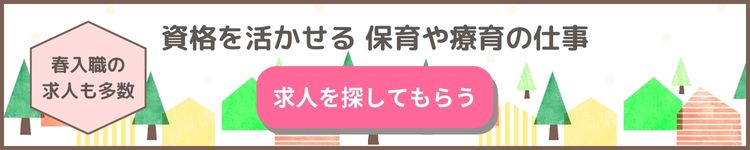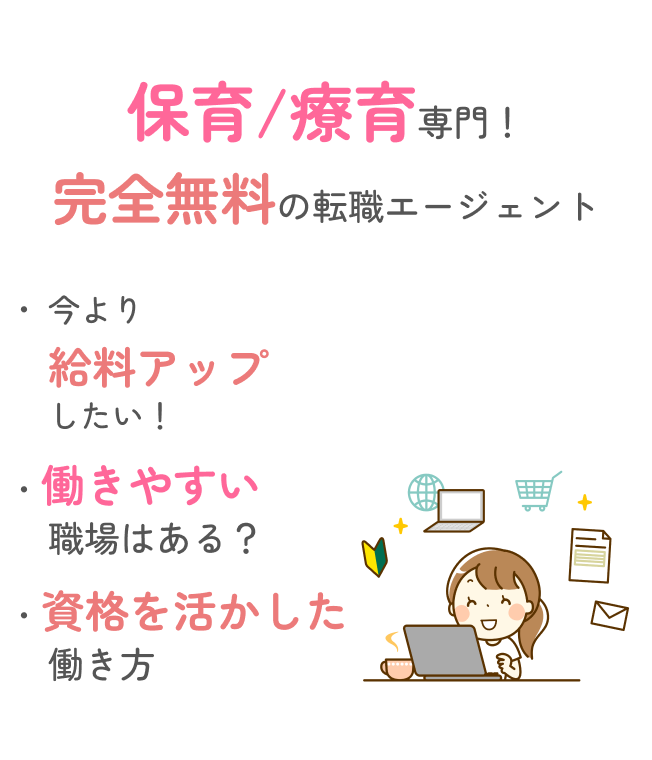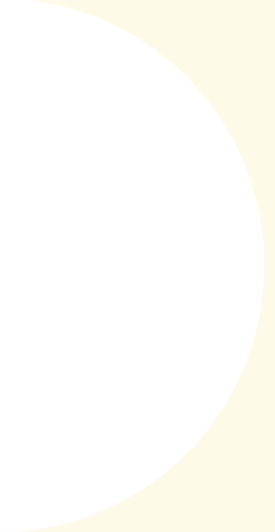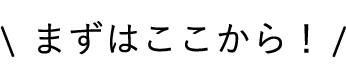この記事では、専門リーダーについて、幅広く詳細に解説します。
国の制度や専門リーダーになるための要件をはじめ、園での役割や他役職との違い、着任するメリットも分かるので、心構えや働き方のイメージができるでしょう。
「すでに専門リーダーとして働いている方」はもちろん「専門リーダーに興味がある方」にとっても、参考になる内容となっています。
専門リーダーとは?
専門リーダーとは、2017年に導入された国の制度「処遇改善等加算Ⅱ」に伴い、新たに設置された保育士のポジションです。
今までは、主任保育士より前の中堅保育士(経験5~10年ほど)に対して、具体的な役職が示されていない状況でした。
それに伴って業務分担が難しい状況や、給料に見合わない偏った仕事量になる状況があったのではないでしょうか。
さらに中堅保育士が就ける役職がないことから、経験を重ねてもキャリアアップができにくい環境であったことも想定されます。
そんな現状を打開するため、中堅保育士のキャリアパスと待遇改善を目的に導入されたのが、国の制度である「処遇改善等加算Ⅱ」で、役職の一つとして「専門リーダー」が位置づけられました。
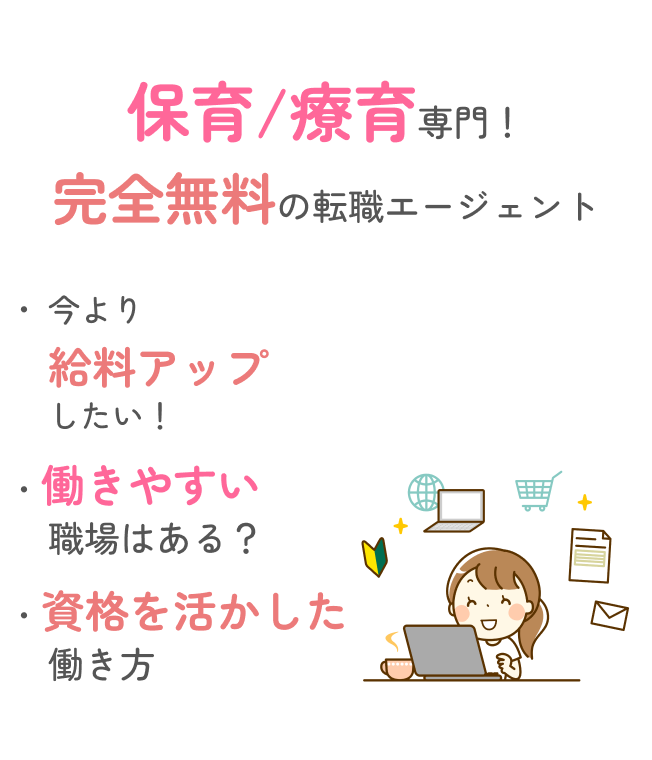

専門リーダーに関する国の制度
前述した通り、専門リーダーの役職は、2017年に導入された国の制度「処遇改善等加算Ⅱ」によって新設されました。
「処遇改善等加算Ⅱ」は、保育士の中堅ポジションを具体化し、キャリアアップのしやすさや、賃金の改善など保育士の処遇を改善することを目的とした制度です。
新たに導入されたポジションは、専門リーダーのほか職務分野別リーダーと、副主任保育士の計3つで、それぞれ役割や要件が異なります。
要約すると、経験年数が3年あれば職務分野別リーダーになることができ、その経験を経て、ライン職の副主任保育士か、スタッフ職の専門リーダーを目指せます。
なお、職務分野別リーダーになると、月額最大5,000円、副主任保育士か専門リーダーになると月額最大40,000円が収入に加算されます。
ただし、加算額は施設によって違いがあるので気をつけましょう。
出典:厚生労働省「保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ」
専門リーダーの役割って?
専門リーダーは、保育の現場においてリーダーとしての責任を果たすスペシャリストです。
ここからは専門リーダーについて、ほかの役職と比較しながら解説していきます。
専門リーダーと役職がついていない一般保育士の違い
大きな違いとしては、任される仕事の役割と給料面です。
一般的に役職のついていない保育士は、1つのクラスを担任や副担任として役割を持って仕事をするのに対し、専門リーダーはクラスの担任をしながらも他クラスとの連携やとりまとめを行なうことがあります。
ただし、園全部のクラスをまとめるというよりも、乳児(0歳~2歳クラス)幼児(3歳~5歳クラス)などの限られた範囲のリーダーとして動くことがほとんどです。
また、園の定員やクラス数が少ない時などは、管理職を支えるポジションとして園全体を見ることもあるでしょう。
専門リーダーと職務分野別リーダーの違い
職務分野別リーダーは読んで字のごとく、「一定の職務を任される」リーダーです。
役割は園によって違いはありますが、
- 「食育」「防災」「保護者支援」など一定の領域を任される場合
- クラス全体や2クラスの連携を任される場合
などが想定されます。
役割の範囲や種類は園の規模、考え方によって違いがありますが、
職務分野別リーダーは役職のない保育士より役割が多いものの、専門リーダーよりも役割の範囲が狭いイメージです。
専門リーダーと副主任保育士の違い
専門リーダーと副主任保育士の決定的な違いは、働き方にあります。専門リーダーが、いわゆるスタッフ職であるのに対し、副主任保育士はライン職(管理業務などの役割が多い)として厚生労働省の資料にも記載があります。
具体的にいうと、専門リーダーは職務分野別リーダーと同じように、保育の現場で働く中で、保育の専門知識やスキルを生かして、課題の解決や若手職員の育成などに取り組みます。
一方の副主任保育士は、保育現場の前線から一歩離れ、組織の管理職をサポートして、組織全体の調整や管理などをメイン業務とします。
専門リーダーと副主任保育士は、役割は違うものの、経験年数などの要件は共通しており、施設における立ち位置は同等です。
ただし、こちらも園によって考え方が違う場合がありますので、役割の詳細は園長や管理職の方に聞いてみましょう。
専門リーダーになるための要件
続いては専門リーダーになるための要件をご紹介していきます。ご興味がある方は是非チェックしていみてください。
具体的には以下の4つです。
- 経験年数が概ね7年以上
- 7分野のうち、4つ以上の分野の研修を修了
- 専門リーダーとして発令
- 職務分野別リーダーを経験
※職務分野別リーダーについては「職務分野別リーダーの役割とは?役職に就くための研修や要件、メリットもご紹介!」の記事で、くわしく解説しています。
専門リーダーになるためには、各都道府県が実施するキャリアアップ研修を4分野(合計60時間)以上、受講しなければなりません。
研修を修了したら、保育園などの勤務先から正式に発令を受け、専門リーダーとして働き始めます。
ただし「研修修了要件」は、これまで適用されておらず、2022(令和4)年度までは、研修を受けずに専門リーダーになることができました。
しかし2023(令和5)年度からは、以下の図の通り、要件が段階的に適用されるようになっています。

出典:「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について(通知)」改正概要
例えば、初年度の2023(令和5)年度に専門リーダーになるためには、1分野(15時間)以上の研修を修了する必要があり、研修を受ける数は1年後になるにつれ、1分野ずつ増えていきます。
具体的には、2024年度(令和6)の場合2分野(30時間)以上、2025年度(令和7)の場合には、3分野(45時間)以上修了することが必要です。
そして、2026年度(令和8)以降に専門リーダーになる場合には、本来の要件通り、前年度中に4分野(60時間)以上の研修修了が求められます。
研修の分野については事項の「専門リーダーになるための研修」で、くわしく説明します。
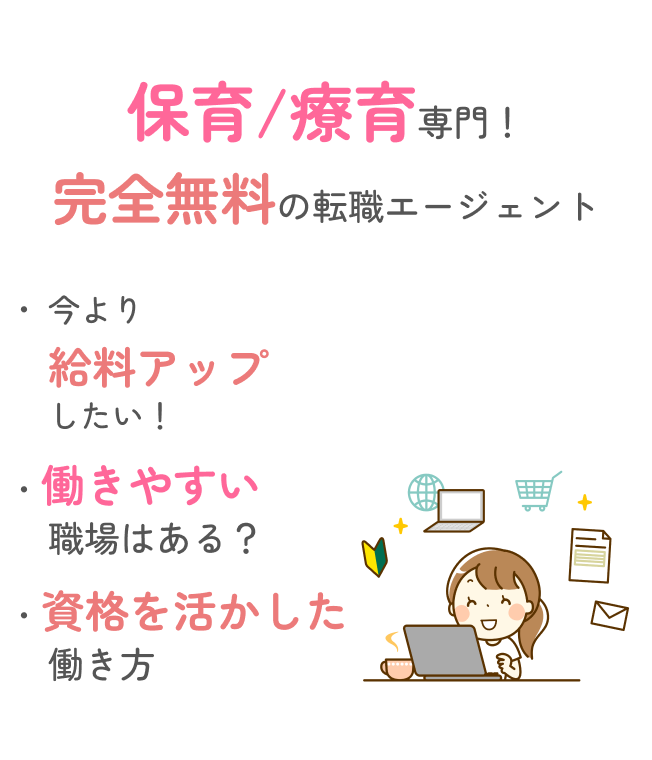

専門リーダーになるための研修
専門リーダーになるためには、所定のキャリアアップ研修を受ける必要があります。
以下7つの専門分野の中から4つの分野を選び、研修を修了します。
| ・乳児保育 ・幼児教育 ・障がい児保育 ・食育・アレルギー ・保健衛生・安全対策 ・保護者支援・子育て支援 ・マネジメント |
研修は1分野につき15時間以上の受講と定められており、修了には2、3日かかります。どの分野の研修も、実践的な能力を身に付けるための内容になっています。
ここからは各研修について、簡単に解説していきますので選ぶ際の参考にしてくださいね。
乳児保育
「乳児保育」の研修では、主に0歳児から2歳児向けの保育について学びます。
乳児保育に関する理解を深めることで、子ども1人ひとりの発達に応じた保育を行う、実践的な能力をつけることを目的としています。
研修の具体的な内容は、以下の通りです。
| ・乳児保育の意義 ・乳児保育の環境 ・乳児への適切な関わり ・乳児の発達に応じた保育内容 ・乳児保育の指導計画、記録及び評価 |
幼児教育
「幼児教育」の研修では、主に3歳児以上に向けての保育について学びます。
幼児教育に関する理解を深めることで、子ども1人ひとりの発達に応じた幼児教育を行う、実践的な能力をつけることを目的としています。
研修の具体的な内容は、以下の通りです。
| ・幼児教育の意義 ・幼児教育の環境 ・幼児の発達に応じた保育内容 ・幼児教育の指導計画、記録及び評価 ・小学校との接続 |
障がい児保育
「障がい児保育」の研修は、障がいへの理解を深め適切な保育計画を立て、1人ひとりの子どもの発達の状態に応じた保育を行う、実践的な能力をつけることを目的としています。
研修の具体的な内容は以下の通りです。
| ・障がいの理解 ・障がい児保育の環境 ・障がい児の発達の援助 ・家庭及び関係機関との連携 ・障がい児保育の指導計画、記録及び評価 |
食育・アレルギー
「食育・アレルギー」の研修では、以下の能力を身につけることを目的としています。
| ・食育への理解を深め、食育計画の作成と活用ができる力 ・アレルギー対応への理解を深め、適切にアレルギー対応を行える力 |
研修の具体的な内容は次の通りです。
| ・栄養に関する基礎知識 ・食育計画の作成と活用 ・アレルギー疾患の理解 ・保育所における食事の提供ガイドライン ・保育所におけるアレルギー対応ガイドライン |
保健衛生・安全対策
「保健衛生・安全対策」の研修では、以下の能力をつけることを目的としています。
| ・保健衛生の理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力 ・安全対策についての理解を深め、適切な対策を講じることができる力 |
研修の具体的な内容は次の通りです。
| ・保健計画の作成と活用 ・事故防止及び健康安全管理 ・保育所における感染症対策ガイドライン ・保育の場において血液を介して感染する病気を防止するためのガイドライン ・教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン |
保護者支援・子育て支援
「保護者支援・子育て支援」の研修は、保護者や子育ての支援について理解を深め、適切な支援を行える、実践的な能力をつけることを目的としています。
研修の具体的な内容は次の通りです。
| ・保護者支援 ・子育て支援の意義 ・保護者に対する相談援助 ・地域における子育て支援 ・虐待予防・関係機関との連携、地域資源の活用 |
マネジメント
「マネジメント」の研修は、以下の能力を身につけることを目的としています。
| ・主任保育士の下でミドルリーダーとして働く際に求められる役割と知識の理解 ・施設の円滑な運営と保育の質を高めるために必要な、マネジメント・リーダーシップ |
研修の具体的な内容は次の通りです。
| ・マネジメントの理解 ・リーダーシップ ・組織目標の設定 ・人材育成 ・働きやすい環境づくり |
専門リーダーになるメリット

ここからは、専門リーダーになるメリットを紹介します。
具体的には、主に以下5つのメリットがあります。
- 専門的な知識とスキルを身に付けられる
- 仕事に役立つさまざまな能力を学べる
- 収入を増やせる
- さらなるキャリアアップを目指せる
- 施設全体の保育の質の向上に貢献できる
専門リーダーの仕事にこれから就く方や、現在専門リーダーの方もぜひ読んでみてください。メリットを把握して前向きに仕事に向き合っていきたいですね。
収入を増やせる
1つ目のメリットは、収入を増やせることです。
専門リーダーになると、月額〜40,000円が給料に加算されます。1ヶ月最大40,000円という金額は、なかなか大きいので、魅力的だと感じる方は多いのではないでしょうか。
ただし、単純にこれまでの給与に40,000円が加算されるわけではないので、注意が必要です。
「処遇改善等加算Ⅱ」によって行政から加算額を直接受け取るのは、保育園などの施設で、そこから皆さんの手元に配分をします。
支給金額の割合は施設側が決めることになるので、40,000円のうち、どの職員にどのくらい支給されるかは雇い主の采配によります。
そのため、同じ「専門リーダー」でも、施設によって支給金額に違いがあることは覚えておきましょう。
仕事に役立つさまざまな能力を学べる
3つ目のメリットは、リーダーシップを発揮できることです。
前述した通り、専門リーダーは保育園内においてリーダー的存在です。様々な職員とコミュニケーションをとるポジションでもありますね。
下記では特に対人関係で身につく能力の一例をご紹介します。
職場によっては「専門リーダー」の立ち位置が違うこともありますが、ぜひ参考にしてみてください。
| ・幅広い職員と関りを持ち、良い関係性を継続できるコミュニケーション能力 ・小さな会議などで話を進めたり、まとめたりするファシリテーション能力 ・さまざまな課題や目標を共有し、達成を目指す推進力 ・後輩や保育士の教育に携わる育成力 ・職員同士が信頼関係を築けるように行動する調整能力 |
専門リーダーとしての仕事は、リーダーシップを発揮して働きたい保育士にとって、魅力的に映るでしょう。
専門的な知識とスキルを身に付けられる
2つ目のメリットは、専門的な知識とスキルを身に付けられることです。
専門リーダーになるには、前述した以下のうち4つ以上のキャリアアップ研修を受けなければなりません。
| ・乳児保育 ・幼児教育 ・障がい児保育 ・食育・アレルギー ・保健衛生・安全対策 ・保護者支援・子育て支援 ・マネジメント |
キャリアアップ研修は1分野当たり15時間以上なので、受講するのに2、3日かかります。4分野の研修を修了するには、10日ほどかけて研修を受講することになります。
これまで保育士が受ける研修は、各施設内で行われるものや自治体が定期開催するものなど、機会が限られていました。
しかしキャリアアップ研修は、全都道府県で横断的に開催されます。興味のある分野の専門知識を学び、スキルをつける絶好の機会と言えるでしょう。
培ってきた保育士としての経験に、最新の知識やスキルが加われば、これまで以上に自信を持って、仕事ができるのではないでしょうか。
さらなるキャリアアップを目指せる
4つ目のメリットは、さらなるキャリアアップを目指せることです。
すでに述べた通り、専門リーダーは中堅保育士が活躍する役職です。
出典:厚生労働省「保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ」
専門リーダーは、園長や主任といった管理職の一段下にあたる位置なので、さらなるキャリアアップも十分目指せるでしょう。
「保育士としてキャリアを積みたい」「いずれは管理職に就きたい」という希望のある方にとっては、経験しておきたいポジションですね。
施設全体の保育の質の向上に貢献できる
5つ目のメリットは、施設全体の保育の質の向上に貢献できることです。
保育園全体の保育の質を上げるためには、1つひとつ解決するべき課題や向上する余地を見つけ、前に進めていくことが必要ですね。
専門リーダーはそのような課題に対して解決策を提示したり、時には周りの人を巻き込んで一緒に課題を解決してくことがあります。
どんな方法で保育の質の向上に貢献できるか一例をあげていきます。
| ・クラスや園全体の課題を明確にして、問題解決を職員と一緒に行なう ・経験や知識をもとに保育士のスキルアップに貢献する ・コミュニケーションを円滑にして、良好な人間関係を構築する |
専門リーダーが組織内でリーダーシップを発揮することで、保育士全体のスキルアップや良好な人間関係をつくることができるでしょう。良い人間関係だと、職員がイキイキ働くことができ、結果的に保育の質が向上に貢献できますね。
専門リーダーの自己評価の書き方
ここからは、現在専門リーダーの方に向けて、自己評価の書き方をご紹介します。
期初や期末、各タイミングで自分の仕事を振り返る際、参考にしてみてください。
保育士の自己評価とは
「保育所における自己評価ガイドライン(2020年改訂版)」によると、自己評価とは「保育所保育指針に基づき、保育の質の確保・向上を図ることを目的に、保育士等及び保育所が自ら行う「保育内容等の評価」」のことです。
簡単にいうと、自身が実践してきた保育を振り返り、明日の保育を良くしていく機会です。
自己評価には、以下のようなメリットがあります。
| ・自分の強みや弱みを把握して、伸ばすべき部分を言語化できる ・できるようになった事が明確になり仕事へのモチベーションに繋げられる ・子どもや保育の気づきを得て、保育の質の向上ができる ・園長や主任から自分の役割や求められていることが明確化できる ・努力している方向が合っているか確認、調整ができる |
参考:厚生労働省「保育所保育指針」
専門リーダーは、以下のような点を意識して自己評価を作成するとよいでしょう。
()内は年度末の振り返り視点になります。
| ・今後のスキルアップ、キャリアアップを考え、どんなスキルを身に付けるか (→期内で必要なスキルを身に付けることができたか) ・専門知識やスキルを、保育の中でどのように活かしていくか (→どのようにスキルを活かせたか。また、その結果どんな良い変化が起こったか) ・知識やスキルを使い、他職員にどう貢献していくか (→周りの職員にどんな貢献をしてどんな効果を与えたか) ・どのような形で、リーダーシップを発揮するか (リーダーシップを発揮できたか、発揮方法が適切だったか) ・園長や主任から期待されている役割は何か (→任された役割範囲は期待されていた状態になっているか) |
以下にそれぞれの例文を挙げるので、参考にしてくださいね。
- 専門知識やスキルを、保育の中でどのように活かしていくか。
| 「食育・アレルギー」のキャリアアップ研修で得た知識を活かし、保育の中で子どもが食に興味・関心を広げられる活動を月に1回以上行なう。 野菜の育成活動を通年で取り入れて、食の大切さを知る機会を作る |
- 知識やスキルを使い、他職員にどう貢献していくか
| 乳児リーダーとして、0歳~2歳の担任を対象に1ヶ月に1回MTGを開く。乳児の発達や行事準備の進捗状況などを持ち寄って、保育の質の向上やスムーズなクラス運営に貢献する。 |
- どのような形で、リーダーシップを発揮していくか
| 積極的に職員とコミュニケーションを図り、各乳児クラスが円滑にクラス運営ができているか、困りごとがないかなど課題の把握や問題解決のために自ら動く。 |
- 今後のスキルアップ、キャリアアップを考え、どんなスキルを身に付けるか
| 専門リーダーとして、各乳児発達における成長過程の理解を更に深めていきたい。今までは実践をもとにした理解と把握が主であったが、今年は論文を月に1本や研修を年間に3回受け専門性を高める。 |
- 園長や主任から期待されている役割は何か
| はじめて専門リーダーとして仕事をする上で、自分がどのような役割を期待されているかを把握しながら、都度主任や園長と方法をすりあわせしていく。また、自ら考えることを基本として自分から担当領域を良くしていく方法を相談する。 |
専門リーダーまとめ

前述したとおり、専門リーダーは2017年に導入された国の制度「処遇改善等加算Ⅱ」に伴い、新たに設置された保育士の役職で、保育の現場でリーダーとしての責任を果たすスペシャリストです。
それまでの保育業界の課題であった、保育士の低賃金や、離職率の高さなどを改善するため、保育士のキャリアアップと待遇改善の、両方をかなえる仕組みとして導入されました。
専門リーダーになる要件は、前述のとおり以下の4つです。
・経験年数が概ね7年以上
・7分野のうち、4つ以上の分野の研修を修了
・専門リーダーとして発令
・職務分野別リーダーを経験
専門リーダーになるには、保育士として7年以上の経験と、職務分野別リーダーとして働いた経験が基本的には必要です。
さらに、キャリアアップ研修7分野のうち4分野(合計60時間)以上、受講の修了が必要です。
4分野の研修を受けるには、10日ほどの必要なことや、施設から専門リーダーとして発令(任命)される必要があり、簡単につけるポジションではないでしょう。
しかし、専門リーダーになると、以下のように多くのメリットが得られます。
- 専門的な知識とスキルを身に付けられる
- 仕事に役立つさまざまな能力を学べる
- 収入を増やせる
- さらなるキャリアアップを目指せる
- 施設全体の保育の質の向上に貢献できる
専門リーダーは、保育士として働く中で「専門的な知識や仕事に役立つ能力を身に付けたい」「キャリアアップを目指したい」と考えている方にとって、経験しておくべき大切なポジションです。
専門リーダーを打診されているなら、保育士として大きく成長できるチャンスだと考え、前向きに検討してはいかがでしょうか。
また反対に「正当な理由が無いのに自分だけキャリアアップをさせてもらえない」「役職についたけど給料と仕事量が明らかにあっていない」など、どうしても自分だけでは解決できない理由で悩んでいる場合は、思い切って転職を考えてみるのも一つの手です。
保育士人材バンクでは、ご希望の条件を伺いながら専任のキャリアパートナーと一緒に一人ひとりにあった転職先を探すことができます。
自分に合った条件で職場を見つけたい方は、是非一度ご相談ください。