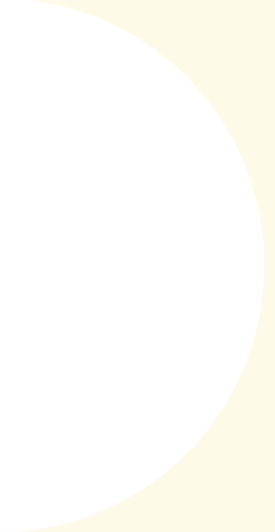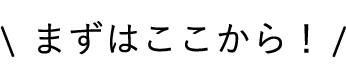低賃金というイメージを持たれがちな保育士ですが、実際のところはどうなのでしょうか。長く働き続けるなら十分な手取りも欲しいところですよね。
今回は、保育士の手取り金額や利用できる制度、そして今後の見通しについて詳しく解説します。


保育士の手取り金額とは?

給与明細を受け取った際、「総支給額」と「手取り額」の違いに驚いた経験はありませんか?
「総支給額」とは、基本給に各種手当を加えた金額のことです。そこから税金や社会保険料、年金などが差し引かれたものが実際の「手取り額」となります。
差し引かれるおもな項目は、次のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 厚生年金
- 健康保険
- 雇用保険
実際の金額は収入や扶養状況、地域によって異なりますが、手取り額は総収入の75~80%になるといわれています。
「なぜこんなに引かれるの?」と疑問を感じる方も多いかもしれませんが、これらの控除項目は将来の年金や医療費補助など、生活の基盤を支えるための制度として必要なものです。
手取り額を知るには、まず給与明細を確認し差し引かれる項目と金額を確かめてみましょう。
保育士の手取りはどのくらい?
ここからは、保育士の年収や手取りについて解説します。
保育士の平均年収と手取り
厚生労働省が2023年(令和5年)に発表している調査結果によると、保育士の平均年収は以下のとおりです。
<保育士の平均年収>
| 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | 平均年収 |
| 264,400円 | 712,200円 | 3,885,000円 |
ただし、手取り額を知るには上記から約ですが75%の金額へと計算する必要があります。
<保育士の平均手取り額>※総支給の75%
| 手取り/月 | 年間賞与その他特別給与額 | 手取り/年 |
| 198,000円 | 534,150円 | 2,913,750円 |
保育士の平均的な手取り月収は約20万円、手取り年収は約290万円です。
保育士の収入は地域によって差が大きく、都市部では基本給が高めに設定されている傾向があります。
ただし、同時に住民税や健康保険料などの負担も増える点に注意です。一方、地方は比較的基本給が低めですが、家賃や生活費が抑えられる地域も多く、手取り額に余裕が出ることもあります。
新卒保育士の平均手取り額
保育士は、経験年数が長いほど収入も高くなっていく傾向があります。年代別の手取りも比べてみましょう。
<保育士の年代別平均手取り>
| 経験年数 | 平均的な手取り |
| 0年 | 約200万円 |
| 1~4年 | 約260万円 |
| 5~9年 | 約280万円 |
| 10~14年 | 約290万円 |
| 15年以上 | 約350万円 |
※「賃金構造基本統計調査/令和5年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」を参考
※平均年収の75%で計算
新卒保育士の場合はまだボーナスが少なく、扶養する家族もいない場合が多いため、控除される税金や社会保険料の割合が比較的高くなります。
そのため、総支給額と手取り額の差が大きく感じられる方も多いでしょう。
役職に就けば基本給だけでなくボーナスも増えるため、相対的に平均年収は上がっていきます。経験年数を重ねるごとに、手取り額も高くなっていくでしょう。


手取りが増えるお役立ち制度

保育士を対象とした制度にはさまざまなものがありますが、ここでは手取りが増えるものにかんして代表的な支援制度を解説します。
処遇改善手当
処遇改善手当とは、保育士の給与に追加で支給される手当のひとつで、保育士の収入アップを目的に導入されたものです。具体的には「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3つの種類があり、経験年数や役職に応じて支給額が異なります。
| 処遇改善加算Ⅰ | 職員の平均勤続年数に応じて加算額が算出される。月額12,000円~最大38,000円(2~12%)ほど。 |
| 処遇改善加算Ⅱ | 副主任保育士や専門リーダーといった役職に就くことで、月額5,000円~40,000円ほど給料が上がる。 |
| 処遇改善加算Ⅲ | 2022年2月から導入されている加算で、月額9,000円が給料に上乗せされる。 |
処遇改善手当は保育士個人ではなく、勤めている保育施設に支給されています。
また、どのように加算額を分配するのかは、施設の方針にゆだねられている点もポイントです。同じ経験年数、同じ役職であっても実際の加算額は施設によって異なります。
借り上げ社宅制度
借り上げ社宅制度とは、保育士が住む住宅にかかる家賃の一部または全額を自治体や保育施設が補助する制度です。
とくに家賃が高い都市部で働く保育士にとって、この制度は生活費の負担を大きく軽減する手段となるでしょう。
たとえば、東京都千代田区では、区内に住む保育士に最大で約月額11万までの家賃補助を行っています。家賃だけでなく共益費や更新料も含まれているのもうれしいポイントです。
借り上げ社宅制度を利用するには、勤務する保育施設がこの制度を導入している必要があります。
また、施設が借り上げている住居に住む必要があり、天引きされる場合は一見手取りが少ないように感じますが、自由に使える生活費を増やしたい方は利用できる施設を積極的に探してみましょう。事前に勤務先や自治体に確認し、利用条件や申請手続きについて理解しておくことをおすすめします。
奨学金返済支援制度
奨学金返済支援制度は、保育士資格取得のために奨学金を利用した方を対象に、返済を支援する制度です。若い保育士の経済的負担を軽減し、長く働き続けてもらうことを目的に設けられています。
奨学金返済制度は自治体によって行われているケースが多く、補助金額にばらつきはあるものの、年間10万円~24万円ほどとなっています。利用条件として、特定の期間その地域や保育施設で働き続けることが求められることが一般的です。
保育士は勤続年数が長いほど年収が上がっていく傾向があり、ベテラン保育士に比べて若手は生活費のやりくりに苦戦している方も少なくありません。そのような方にとって、月々の支出を抑えられる返済支援制度は心強いものになるはずです。
就職準備金貸付
就職準備金貸付制度は、新人保育士が就職する際に必要な費用を補助するためのものです。20万円~40万円程度の貸付けを受けられ、就職後に同じ自治体の保育施設で一定期間勤務することで返済が免除されます。
この制度では、引っ越し費用やスーツをはじめ、教材購入費などに利用されることが一般的です。就職にともなう出費を減らし、経済面での不安のない状態でスムーズな就職が可能になります。地域や運営団体によって条件が異なるため、詳細は自治体の福祉事務所や保育士養成施設に問い合わせてみましょう。
未就学児をもつ保育士の子ども預かり支援
未就学児をもつ保育士が仕事と家庭を両立しやすくなるよう、預かり保育の利用料を支援する制度があります。
たとえば、埼玉県では保育料の一部を無利子で貸し付け、一定期間保育士として勤務を続けることで返済が免除される仕組みとなっています。このような支援制度は、家庭を支える保育士にとって大きな助けとなるでしょう。各自治体によって条件や内容が異なるため、勤務先の自治体に確認することをおすすめします。
今後、保育士の手取りは増えるの?
令和6年11月22日、こども家庭庁は「保育士等の処遇の抜本的な改善」として、保育士の手取りを増やす目標を発表しました。具体的には、保育士などの人件費を10.7%引き上げるという内容です。
これまでも保育士の処遇改善は行われてきましたが、加算額がそのまま保育士の手取りに反映されていないケースも多く、制度の改善が必要とされています。共働き世帯が増え、今後ますます多様になっていく保育ニーズに対応するためには、保育士不足の解消や、保育士の働きやすさの向上は欠かせません。
国が主導となって保育士支援に力を入れていくという報告は、保育士にとってうれしいニュースです。手取りが上がる可能性も高いので、今後の動向も楽しみですね。


保育士の手取りを増やす方法

保育士の手取りも増やそうと国や自治体も力を入れて改善している最中ですが、少しでも手取りを増やすなら自身も積極的に動いていきましょう。収入アップに効果的な方法として、以下3つを解説します。
キャリアアップを目指す
保育士の手取りを上げる方法のひとつが、保育士キャリアアップ研修を修了し、役職につくことです。この研修の修了が、保育士の処遇改善制度の要件となっており、「職務分野別リーダー」や「専門リーダー」「主任保育士」などの役職に就くと、施設に支給される手当が加算されます。
実際にどのくらい手取りが増えるのかは施設や役職の人数によって異なりますが、最大月40,000円の手当がもらえる可能性もあり、保育士の収入アップに大きな影響を及ぼすポイントです。
保育士キャリアアップ研修制度は、役職や処遇改善そのものにもメリットがありますが、受講資格を得るまでの経験年数や研修で身に付く知識やスキルも大きな実りとなります。勤務している施設でキャリアを目指せるのはもちろん、修了後は都道府県を超えて実績やスキルの証明ができるのも強みです。手取りの多い施設への転職もしやすくなり、保育士としてキャリアの幅が広がるでしょう。
もし現在、派遣保育士や契約職員、フルタイムパートなどで働いている場合、はじめに目指すのは正社員登用です。正社員を募集している施設や、正社員登用制度のある施設への転職が手取りを増やす近道となるでしょう。
制度の活用を徹底する
借り上げ社宅制度や奨学金返済支援制度など、保育士が利用できるさまざまな制度を活用し、生活費や実質的な負担を軽減することも大切です。
たとえば、借り上げ社宅制度を利用すると、実際の手取りは少ないように感じても、住居費が抑えられているぶん生活費として使える金額には十分なゆとりがあるケースもめずらしくありません。同じように奨学金返済支援制度を利用する場合も月々の返済負担が減り、手取り額が増えるでしょう。
さらに、地方自治体が行っている独自の補助金や支援も見逃せません。これらの制度は地域によって内容が異なるため、自治体が保育士にどのような支援を行っているのかを確認し、自分に合った制度は積極的に利用していきましょう。事前の情報収集が生活費のコストを下げ、手取りアップのカギとなります。
幼稚園免許取得を目指す
幼稚園教諭と保育士の資格を両方取得し、就職の幅を広げることも収入アップにつながりやすいでしょう。近年施設数が増えている認定こども園のうち「幼保連携型認定こども園」については原則として幼稚園教諭と保育士の両方の資格が必要です。
ただし令和11年度までは、どちらかの資格を持っていれば働ける経過措置が取られています。すでに認定こども園は広く普及しており、いずれ両方の資格を持つ方が求められるようになるでしょう。(2025年4月現在の情報)
経過措置の期間中は、保育士の資格を持つ方が幼稚園免許を取得する場合に必要な単位数を減らせる特例も設けられています。この期間中がふたつの資格を取得するチャンスです。保育園や幼稚園だけにかかわらず、認定こども園などさまざまな選択肢が持てるようにしておけば、良い条件の求人を見たときにすぐにアクションを起こせるでしょう。
また、保育士と幼稚園教諭は施設においての役割が異なりますが、子どもの個性や生活リズムを尊重しつつ、幼稚園の特色である教育についても知識やスキルを深めておけば、教育・保育どちらの分野でも重宝される人材になります。自分の可能性を広げたい方は、ぜひダブル取得について検討してみてください。
どうしても手取りが増えない場合は

すでに働いている施設で収入が上がることがベストですが、難しい場合は転職も視野に入れる必要があります。収入などの条件を重視して転職する場合に、おすすめの方法を3つご紹介します。
支援制度が手厚い自治体、もしくは手当が充実している保育園を選ぶ
今回紹介した自治体の制度や住居費を抑えられる手当などは自治体、もしくは保育施設によって導入状況が異なります。手取り収入を少しでも増やしたい方は、資格手当や役職手当が豊富な保育園や、借り上げ社宅制度を利用できる自治体を選ぶことが大切です。場合によっては、地域を変える選択肢も出てくるでしょう。
地域の取り組みは、自治体の公式ホームページで確認できます。保育園の手当については求人情報にしっかりと目を通し、基本給以外の条件や手当も調べることが大切です。求人情報を確認する方法はいくつかありますが、なかでも保育専門の求人サイトや転職サイトは一般の求人情報よりも細かな情報が確認できるのでおすすめです。
転職エージェントを利用する
たくさん保育施設のなかから候補を絞ったり、自分に合った施設を見つけたりすることが難しい場合には、転職エージェントを利用してみましょう。転職エージェントの大きなメリットは、自分に変わって希望の条件に合った職場を探し、転職活動をスムーズに進められることです。
たとえば収入を重視した転職なら、「手当が充実」「住宅に関する支援が受けられる」「ボーナスが手厚い」などの希望をあらかじめ伝えておくと、ぴったり合う求人を紹介してもらえます。
また、サービスによっては一般に知らされていない非公開求人なども扱っているため、エージェントを通じて条件の良い求人を見つけやすいのも魅力です。働きながら転職を勧めたい方や、より良い条件で働きたいと考えている保育士にとって、エージェントの利用は便利で効果的といえるでしょう。
保育士の手取りまとめ
自治体の支援制度や、勤めている施設独自の手当などは、保育士の手取り額に大きな影響を及ぼします。
現状のままキャリアアップを目指し、収入を上げていくことも大切ですが収入アップを重視する場合は転職も効果的です。
希望する地域や施設の情報を確認し、自分に合った施設を探してみましょう。

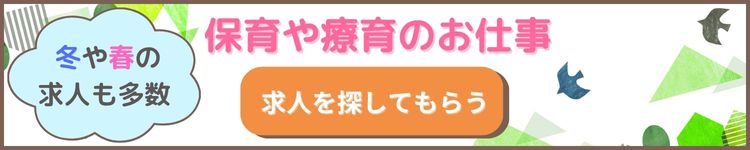








は可能?バレる?おすすめは?税金や確定申告、法律上の注意点!【保育士人材バンク】-scaled-e1752724218671.jpg)