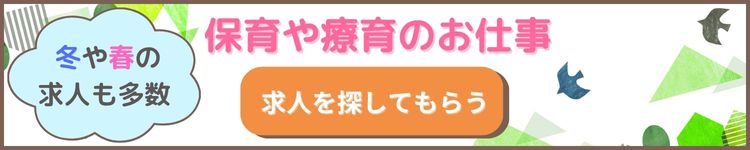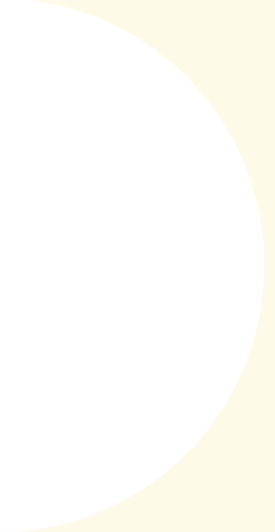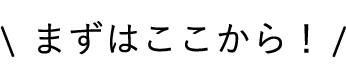施設保育士は、一般的な保育園以外の児童福祉施設で働く保育士です。
2025年5月現在、施設保育士の働く施設はおおむね9つあります。今回は、施設保育士の働く9つの職場や仕事内容について、1つずつ紹介します。施設保育士に興味のある方は、ぜひご一読ください。


施設保育士とは
施設保育士というのは、保育園以外の児童福祉施設で働く保育士のことです。
児童福祉施設には12の施設がありますが、その中で保育士資格を持つ保育士の配置を求めている児童福祉施設は、以下の9つです。(2025年5月時点)
- 児童養護施設
- 障がい児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童厚生施設
- 児童自立支援施
- 児童家庭支援センター
参考:e-Gov 法令検索「児童福祉法」
文部科学省「保育士資格を有する者の配置を求めている児童福祉施設等」


施設保育士の仕事内容
施設保育士の職場は、保育や教育・福祉などさまざまな業界・業種なので、職場によって仕事内容が異なります。
中には子どもたちが入所し生活を送る施設もあり、そのような職場では、保育士を含む職員が24時間体制でシフトを組んで仕事をします。
ここからは、前述した施設保育士の職場それぞれの仕事について、解説していきます。
児童養護施設
児童養護施設は、1~18歳の保護者のいない子どもや、家庭の事情で保護者と一緒に暮らせない子どもを、養育するための施設です。
児童養護施設の入所児童の平均在籍期間は4.6年で、10年以上の子どもも1割程度います。
近年では、虐待を受けた子どもや障がいのある子どもの入所が増えてきており、専門的なケアの必要性が高まっています。
保育士は、このような子どもたちを対象に、家庭的な環境を整え、生活指導や学習指導などのサポートを行います。
障がい児入所施設
障がい児入所施設は、主に身体・知的・精神面に障がいがあり、自宅で生活を送るのが難しい0~18歳の子どもたちが生活するための施設です。
障がい児入所施設には、「福祉型」と「医療型」の2種類があり、それぞれサービスの対象と内容が異なります。
| 福祉型障がい児施設 | 医療型障がい児施設 | |
| 対象 | ・身体障がい ・知的障がい ・発達障がいを含む精神障がい | ・自閉症を含む知的障がい ・肢体不自由 ・重症心身障がい |
| サービス内容 | 日常生活の支援が中心 | 治療や管理など、医療的ケアを含む生活支援を行う |
重度の障がいや、障がいの重複などで医療支援の必要な子どもは医療型、医療支援が必要ない子どもは福祉型の施設に入所します。
保育士は、入所している子どもたち1人ひとりの障がいに合わせた、日常生活の援助や介護、訓練などのサポートを行います。
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、児童発達支援施設の1つです。障がいのある未就学の子どもを対象に、通所による発達支援(療育)を行います。
児童発達支援センターも、福祉型と医療型の2つに分かれています。
福祉型が身体、知的・発達障がいを含む精神障がいのある子どもを対象とする一方で、医療型は上肢・下肢・体幹機能に障がいのある子どもを受け入れ、医療的ケアも行います。
前述した通り、児童発達支援センターの役割は、通所による発達支援(療育)がメインです。
しかし、支援センターは単なる「事業所」とは異なり、療育を行うためだけの施設ではありません。地域の中核を担う施設のため、事業内容は以下のように多岐にわたります。
| ・家庭や保護者の相談・支援 ・保育所や学校への訪問支援 ・関係機関との連携 ・「児童発達支援事業所」の支援 |
児童心理治療施設
児童心理治療施設は、心理的・情緒的な問題から日常生活を送るのが難しい子どもたちに、心理治療を中心とした治療や支援を行う施設です。
子どもの年齢は小・中学生を中心とした20才未満で、入所や宿泊・通所で治療を行います。
児童心理治療施設で保育士が担当するのは、主に生活指導です。
多くの子どもが家族から離れて集団生活を送るため、快適で安心できる環境整備を行い子どもたちと日々の遊びやスポーツ、作業などを通して交流を深めます。
誕生日会や学園祭、キャンプやクリスマス会など、行事のイベントやレクリエーションの企画・運営を行うこともあるでしょう。
乳児院

乳児院は、家庭の事情などで、保護者が自分で養育できない乳幼児の養育を行う施設です。
預かるのは乳児が中心ですが、場合によっては就学までの幼児を預かることもあります。
在所期間はさまざまですが、およそ半数が半年以内の短期です。在所が長期間にわたる場合には、子どもの養育だけでなく、保護者支援や退所後のアフターケアも行います。
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している母子家庭や、何らかの事情で母子家庭の状態となっている女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。
施設では母子が生活できる居室を提供しており、職員が常駐しています。設置されている都道府県によって、保育士の配置が認められている場合があります。
母子生活支援施設で生活する子どもは、基本的には学校・保育所に通いますが、放課後や長期の休みには、保育士が遊びや日常生活の援助を行います。
子ども会活動や季節ごとの行事、文化・スポーツ活動などの集団活動を企画・運営することもあるでしょう。
児童厚生施設
児童厚生施設とは、「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を
ゆたかにすることを目的とする児童福祉施設」のことで、児童館や児童遊園を指します。
児童館は屋内型、児童遊園は屋外型の施設で、その両方に「児童厚生指導員」という、子どもの遊びを指導する専門員の設置が義務付けられています。
保育士は、児童厚生施設で「児童厚生指導員」として働きます。
指導員は、放課後や休日、長期休みの日中に施設を訪れる子どもたち(主に小学生)を対象に、運動や遊び、読書、学習の場を提供します。
施設によっては、子育て中の保護者が利用できる「子育てサロン」を開催し、育児相談を行ったり、親同士の交流の場を設けたりすることもあります。
児童自立支援施設
児童自立支援施設は、家庭の事情を含むさざまな生活指導などを必要とする子どもを入所させる施設です。
1人ひとりの子どもに必要な指導を行って自立を促し、退所後も通所で支援を続けます。
子どもたちは、家庭的な雰囲気の寮で、職員と共に規則正しい集団生活を送ります。
小・中学生は、日中は施設内にある学校に通い中学校を卒業すると、施設内の高等部か外部の一般高校へ通って自活・自立訓練を積み、退所に向けた準備をします。
保育士が児童自立支援施設で働く場合、「児童生活支援員」として、子どもたちの生活のサポートにあたります。
安心感のある生活環境を整え、子どもとの関係を築き、ともに生活を送り、活動を行う中で、信頼関係を育んでいくことが大切です。
保護者との面談や家庭訪問を行い、家庭環境の調整に携わることもあるかもしれません。
児童家庭支援センター
児童家庭支援センターは、地域の家庭の子育てや子どもに関する相談に対応する施設です。
現状、児童養護施設や乳児院、児童心理治療施設などに併設されたセンターが多く、具体的には以下5つの事業を行っています。
| ・子どもに関する家庭からの相談で、専門的な知識や技術の必要なものへの対応 ・市町村の依頼に応じ、職員や講師派遣などによる技術的助言や必要な援助 ・児童相談所への通所が困難な子どもや、退所後間もない子どもの指導や相談援助 ・里親及びファミリーホームからの相談対応など、必要な支援 ・児童相談所や市町村、里親、児童福祉施設、学校などとの連絡調整 |
拠点とする地域のニーズに合わせて子どもに関する支援を行っています。
保育士の資格を持っていると、児童家庭支援センターで働けます。子どもや保護者の問題解決のための相談業務が、主な仕事となるでしょう。
求人の探し方
施設保育士の求人を探すには、以下のような方法があります。
| ・ハローワーク ・就職・転職サイト ・転職エージェント |
特定の地域で働きたいなら、ハローワークの利用ができます。地域に根付いているハローワークであれば、さまざまな可能性を提示してくれるでしょう。
各地方自治体のホームページから、求人情報を探すのも一つの手です。
この方法なら、自治体が発信する、確実な情報を得られます。しかし一方で、1つひとつのHPを自分で確認しなければならず、情報収集に時間と手間がかかってしまうのが難点です。
就職サイトや転職サイトでも、特定の職場をキーワードとして検索すると、求人を見つけられる可能性があるでしょう。
求人数の少ない施設保育士の求人を探すには、転職エージェントの活用も効果的です。
転職エージェントなら、自分の希望に合った転職先を紹介してくれるほか、業界や分野に関する情報提供や、非公開求人の紹介が受けられることもあります。
転職エージェントの1つ「保育士人材バンク」では、履歴書の添削や面接対策といった、手厚いサポートも受けられますよ。
施設保育士として働くことや就職・転職活動に、不安があるのなら、活用してみてはいかがでしょうか。
施設保育士まとめ
施設保育士というのは、保育園以外の児童福祉施設で働く保育士のことです。
2025年5月時点で、保育士の配置を求めている児童福祉施設は、以下の9つあります。
| ・児童養護施設 ・障がい児入所施設 ・児童発達支援センター ・児童心理治療施設 ・乳児院 ・母子生活支援施設・児童厚生施設・児童自立支援施・児童家庭支援センター |
参考:e-Gov 法令検索「児童福祉法」
文部科学省「保育士資格を有する者の配置を求めている児童福祉施設等」
一般的に、上記9つの児童福祉施設で働く保育士のことを「施設保育士」と呼びます。
施設保育士の求人は、一般的な保育園よりも少なく、全国的に見ても狭き門なので、就職・転職活動が難航する可能性が十分あります。
そんなときには、転職エージェント「保育士人材バンク」を活用してはいかがでしょうか。