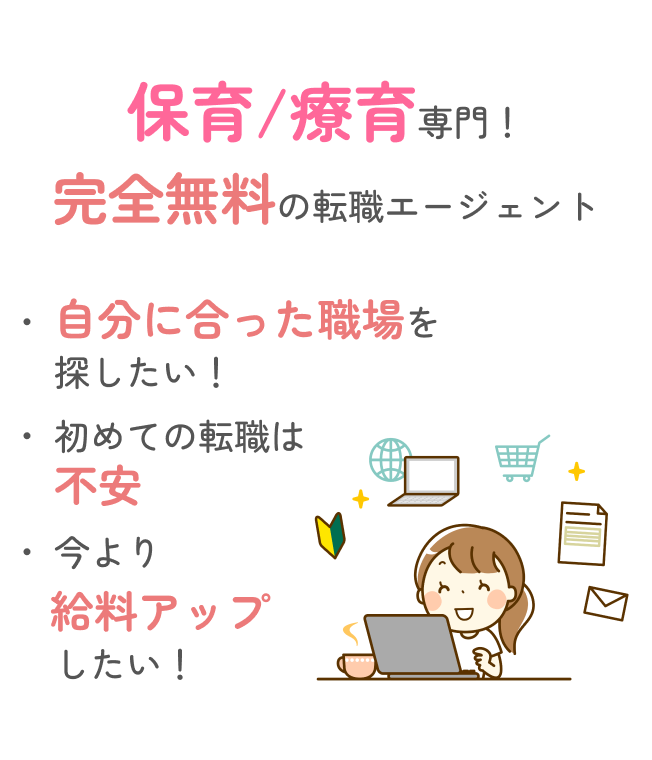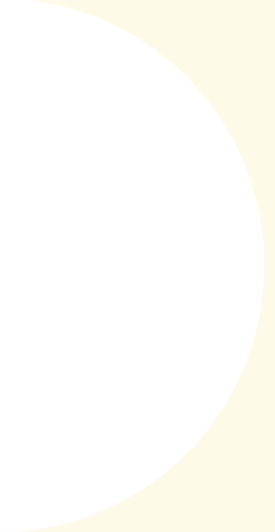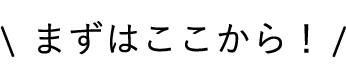「保育士になりたいけれど、試験は難しいのかな?」そんな疑問をもつ方も多いのではないでしょうか?
保育士試験は、独学で保育士資格を取得するために避けては通れないステップです。筆記と実技の2段階でおこなわれ、合格率も気になるポイント。
この記事では、保育士試験の流れや実技試験の内容、合格率まで詳しくご紹介します。
保育士試験とは
保育士試験とは、国家資格である『保育士資格』を取得するための全国統一試験です。保育士養成学校に行かず独学で保育士資格を活かした仕事をしたい人にとって重要なステップとなります。
試験は、筆記試験と実技試験の2段階で構成されており、筆記試験に合格した人だけが実技試験へ進む仕組みです。
毎年多くの受験者が挑戦しており、合格すれば正式に保育士として登録できるようになります。まさに「子どもと関わる仕事をするための第一歩」といえる大切な試験です。
保育士試験の内容
保育士試験は、知識を問う筆記試験と、実際の保育スキルを確認する実技試験で構成されています。ここでは、それぞれの試験内容について詳しく解説します。
筆記試験
筆記試験は全科目マークシート方式で実施され、保育に関する専門知識や子どもの発達、福祉に関わる幅広い分野から出題されます。問題数が多く、暗記だけでなく理解を伴った学習が必要とされるのが特徴です。
出題される科目は以下の9科目です。
- 保育の心理学
- 保育原理
- 教育原理
- 社会的養護
- 児童家庭福祉
- 社会福祉
- 保育実習理論
- 子どもの保健
- 子どもの食と栄養
各科目ごとに6割以上の得点をとることが合格ラインとなり、1科目でも基準に達しないと筆記試験は不合格になります。そのため、得意分野だけに偏らず、苦手科目の克服がとても重要です。
また、保育士試験には科目別の合格制度があり、一度合格した科目は3年間有効とされています。すべてを一度で合格する必要はないため、計画的に挑戦できるのも大きな特徴です。
筆記試験は範囲が広いため、テキストの基本事項を押さえたうえで、過去問を繰り返し解きながら出題傾向をつかむのが効果的です。
筆記試験に合格した人だけが次の実技試験に進める仕組みになっており、まさに保育士試験突破の第一関門といえます。
実技試験
実技試験は「音楽表現」「造形表現」「言語表現」の3分野の中から2つを選んで受験します。内容は実際の保育現場を想定しており、子どもと接する際に必要となる実践力や表現力が試されます。
- 音楽表現・・・課題曲をピアノなどの楽器で演奏しながら歌う試験です。演奏技術だけでなく、子どもが楽しめるような歌い方やリズム感も評価の対象となります。
- 造形表現・・・テーマに沿った絵を一定時間内に描く試験です。絵の技術そのものよりも、保育の場面をイメージできる力や構図の工夫が重視されます。
- 言語表現・・・課題に沿ったお話や絵本の読み聞かせをする試験です。子どもに分かりやすい声のトーンや抑揚、間のとり方が評価されます。
どの分野も専門的な技術より、「子どもに伝わる表現力」が重要視されるため、完璧を求める必要はありません。自分の得意分野を活かしつつ、日頃から練習して慣れておくことが合格への近道です。
筆記試験に続いて実技試験もクリアすることで、はじめて保育士資格を取得することができます。
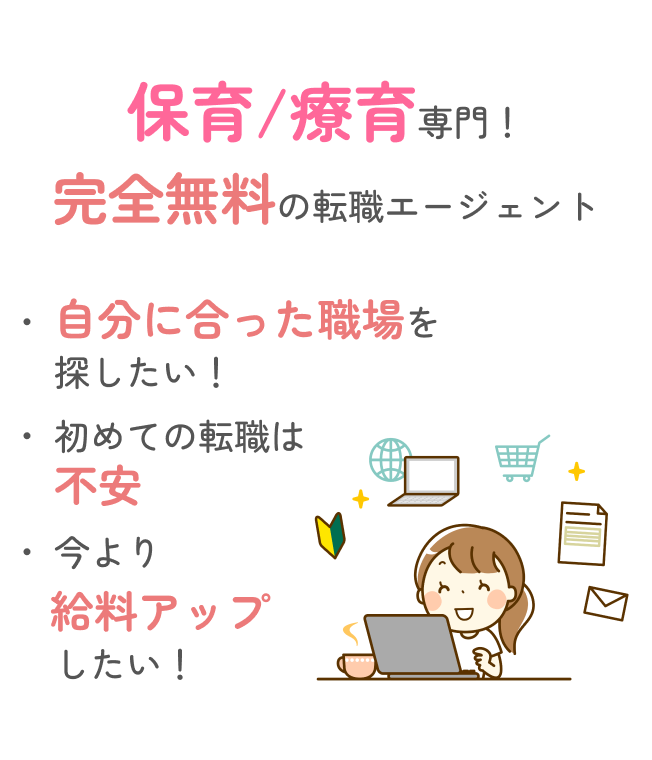

保育士の合格率
厚生労働省の統計によれば、2023年(令和5年)の保育士試験合格率は26.9%でした。(受験者66,625人中、合格者17,955人)
2010年(平成22年)には11.4%と一桁台に近い数字だったことを考えると大きく改善されています。
保育士試験合格者数の年度ごとの変化
保育士試験合格者数の動向を、過去5年の受験者データから見てみましょう。
▼保育士試験 合格率データ
| 年度 | 受験申請者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2019年(令和元年) | 77,076 | 18,330 | 23.8% |
| 2020年(令和2年) | 44,914 | 10,890 | 24.2% |
| 2021年(令和3年) | 83,175 | 16,600 | 20.0% |
| 2022年(令和4年) | 79,378 | 23,758 | 29.9% |
| 2023年(令和5年) | 66,625 | 17,955 | 26.9% |
上記の表からも分かるように、保育士試験の合格率はおおむね20~30%前後で推移しています。令和3年は20.0%とやや低めでしたが、令和4年には29.9%と大きく上昇しており、年度によって変動があることが分かります。
前期と後期の合格率の違い
保育士試験は前期・後期ともに同じ基準でおこなわれますが、実際の合格率を見てみると、微妙な差が見られます。令和5年のデータをもとに比較してみましょう。
▼前期・後期ごとの合格率
| 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1回目試験(前期) | 34,380人 | 9,612人 | 27.9% |
| 2回目試験(後期) | 28,683人 | 7,553人 | 26.3% |
上の表から分かるように、前期(1回目)の合格率は27.9%、後期(2回目)は26.3%となっており、大きな差はありません。
出題範囲や合格基準はどちらも同じため、難易度自体に違いはないといえるでしょう。
参考:
厚生労働省「保育士試験の実施状況(令和5年度)」
厚生労働省「保育士試験の実施状況(令和4年度)」
厚生労働省「保育士資格関係資料」
厚生労働省「保育士の現状と主な取組」
保育士試験の受験条件
保育士試験を受験するためには、学歴や実務経験など一定の条件を満たす必要があります。
学歴による受験条件
短大や大学で保育士養成課程を修了した人は、保育士試験の受験資格を持ちます。また、指定科目を履修した専門学校卒業者も対象です。
さらに、一般の大学・短大卒業者であっても、科目等履修や通信制大学を利用して必要単位を修得すれば受験が可能です。
実務経験による受験条件
高卒の人でも、児童福祉施設などで5年以上かつ7,200時間以上勤務していれば、受験資格が得られる可能性があります。
該当施設が受験資格認定基準を満たすかどうかについては、各施設の所在する都道府県へお問い合わせください。
学歴以外のルートとして、社会人から保育士を目指す人に多く選ばれている方法です。
参考:全国保育士養成協議会「受験資格認定(知事認定)の申請方法」
特例制度による受験条件
幼稚園教諭免許状をもち、指定の児童福祉施設などで3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を積んでいる場合、特例制度を利用して保育士資格取得の際に特定の科目が免除されます。(2025年8月現在)
さらに、2023年(令和5年)4月以降は、新たに「幼保2年特例」が導入されました。
幼保連携型認定こども園において2年以上、合計2,880時間以上勤務した保育教諭については、必要な特例教科目8単位のうち2単位を修得したものと扱われます。
参考:子ども家庭庁「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」
誰でも受験できるケースはある?
保育士試験は、学歴や性別、年齢に関係なく「希望すれば誰でも受けられる」というわけではありません。しかし、公的に認められた教育機関・制度を通じて要件を満たせば、受験資格を得ることが可能です。
たとえば、通信制大学で必要な単位を取得することで条件をクリアできるケースもあります。
そのため、条件が足りないと感じる方は、まず自分が利用できる学習ルート(通信制大学や専門学校への進学など)を整理してみることをおすすめします。
参考:
全国保育士養成協議会「受験資格詳細」
厚生労働省「保育士資格取得の特例の概要」
保育士試験の申込方法
保育士試験は、例年「前期」と「後期」に分けて実施されており、申込方法も全国で統一されています。ここでは申込の流れや注意点について詳しく解説します。
申込方法の流れ
保育士試験の申込は、インターネット申込と郵送申込の2通りが用意されています。
一つ目は、『一般財団法人 保育士試験事務センター』公式ホームページからおこなうインターネット申込です。オンラインで必要事項を入力した後、指定された書類を郵送する形になります。
二つ目の郵送申込の場合は、事前に願書を取り寄せて記入し、必要書類と一緒に送付する必要があります。
どちらの場合も不備があると受験できなくなるため、入力内容や書類は必ずコピーをとるなどして控えを残しておきましょう。
申込期間と受付時期
保育士試験は毎年、前期(4月実施)と後期(10月実施)の2回に分けておこなわれ、それぞれの申込期間が決まっています。
例年では、前期は1月頃、後期は7月頃に受付が開始されます。
受付期間は数週間程度と限られており、1日でも過ぎてしまうと申込が無効になります。とくに郵送の場合は余裕をもって準備を始めることが大切です。
提出が必要な書類
申込の際には、自分の受験資格を証明するための書類が必要です。代表的なものには、大学・短大の卒業証明書や在学(修了)証明書、高校卒業後に保育関連施設で勤務している方は勤務証明書などがあります。
勤務証明書は発行までに時間がかかることが多いため、勤務先に早めに依頼しておくのがおすすめです。条件によって必要書類が異なるため、公式案内を必ず確認し、自分のケースに合わせて揃えるようにしましょう。
受験料について
保育士試験の受験料は、前期・後期ともに同額で12,700円です。(2025年時点)
ただし、受験の手引き(願書)や手数料などがかかるため、実際の費用はオンライン申請で13,050円、郵送申請では13,963円となります。
また、1科目のみの受験でも、全科目を受験しても費用は変わりません。申込時に必ず最新の受験料を確認し、間違いのないように支払いましょう。
支払い方法は銀行振込のほか、インターネット申込ではクレジットカード決済が利用できるケースもあります。
受験料の納付が確認できなければ申込が成立しないため、決済完了の証明を必ず手元に残しておくことが大切です。
参考:全国保育士養成協議会「受験申請方法」
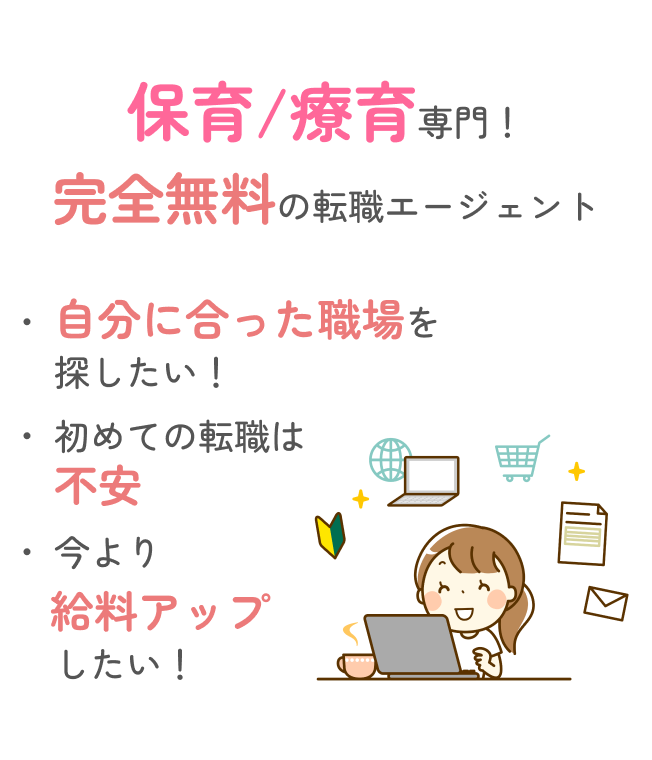

保育士試験に合格するために必要なこと
保育士試験は、毎年多くの人が挑戦しますが、合格率は20~30%前後と決して高くはありません。効率よく学習し、合格を勝ち取るためには計画的な勉強や実技への準備が欠かせません。
ここでは、保育士試験に合格するためにとくに意識しておきたいポイントをご紹介します。
最新の試験情報を確認する
保育士試験の制度や試験内容は毎年更新される可能性があるため、最新情報を把握しておくことが合格への第一歩です。
最新情報を把握せずに準備を進めると、申込漏れやスケジュールのずれなどが起こりやすくなります。とくに申込期間やオンライン申請の開始タイミングは変わる可能性があるため、試験情報をこまめにチェックする習慣をつくると安心です。
学習計画を立てて継続する
筆記試験は全9科目と範囲が広いため、行き当たりばったりで勉強を始めると途中で挫折しやすくなります。最初に全体の試験日程から逆算して「どの科目をいつまでに仕上げるか」をスケジュール化することが大切です。
たとえば、1日30分でも良いので、無理のない範囲で毎日続ける習慣をつくりましょう!カレンダーや学習アプリを活用して進捗を可視化すると、モチベーションの維持にもつながります。
過去問や模擬試験で実践力をつける
過去問は試験対策の基本であり、繰り返し解くことで出題傾向やよく問われるテーマが見えてきます。同じ問題を解き直すうちに知識が定着し、得点力も自然と高まります。
また、模試試験を受けることで本番さながらの緊張感を体験でき、時間配分や解答スピードの練習にもなります。
とくにマークシート形式では、迷った問題に時間をかけすぎない判断力も重要です。
苦手分野を早めに克服する
保育士試験は科目ごとに6割以上の得点が必要なため、得意科目だけで点数を稼いでも不合格になる可能性があります。そのため、苦手分野を早めに見つけて重点的に学習することが合格への近道です。
たとえば、「児童家庭福祉が苦手」という場合は、過去問の出題範囲をまとめて整理し、テキストの基本部分を繰り返し読み込むことから始めましょう。
短期間でも毎日触れることで知識が積み重なり、弱点の克服につながります。
実技試験の準備を怠らない
筆記合格後に受ける実技試験では、音楽・造形・言語の中から2分野を選びます。
普段からピアノや絵の練習、絵本の読み聞かせなどをおこない、表現力を磨いておくことが合格につながります。
ピアノに苦手意識がある方は、無理に難しい曲を弾く必要はなく、課題曲を基本に沿って丁寧に演奏できれば十分評価されます。また、実技試験では造形や言語を選択することもできるため、自分の得意分野を活かして挑戦することも可能です。
モチベーションを維持する工夫を取り入れる
保育士試験は学習範囲が広く、長期間にわたって勉強を継続する必要があります。そのため、知識面の努力だけでなく、気持ちを切らさず学習を続ける工夫も欠かせません。
たとえば、小さな目標を設定して達成感を積み重ねることは効果的です。「今日は問題集を1章進める」「今週は過去問を20問解く」など短期目標をクリアしていくことで、自信とやる気につながります。
また、仲間や家族に学習状況を共有するのもおすすめです。周囲に応援してもらえることでモチベーションが高まり、試験まで走り抜けやすくなります。
勉強ばかりでは疲れてしまうため、適度な休憩やリフレッシュの時間を取り入れることも大切です。散歩や軽い運動をするだけでも気分が切り替わり、集中力を保ちやすくなります。
モチベーションを維持する工夫を取り入れることで、長い試験勉強を乗り越えやすくなり、合格への道がグッと近づきます。
保育士試験の解答速報
保育士試験を受験された方にとって、試験後すぐに気になるのが「自分の解答が正しかったのか」「合格点数に届いているのか」という点ではないでしょうか?
そのようなときに役立つのが解答速報です。自己採点を通じておおよその合否を確認できるため、次の実技試験に向けた準備や、再受験に備えた学習計画を早めに立てることができます。
保育士人材バンクでは、試験直後に解答速報を公開しています。受験者の皆さまがいち早く自己採点できるよう情報を提供しており、多くの方にご活用いただいています。
試験を終えた皆さまが自信をもって次の一歩を踏み出せるよう、これからも保育士人材バンクは応援してまいります!
保育士試験のまとめ
保育士試験は、筆記試験と実技試験の2段階でおこなわれる国家資格であり、合格率は例年20~30%前後と決して高くありません。
そのため、計画的な勉強や実技対策にくわえ、受験条件や申込方法を早めに確認しておくことが合格への第一歩になります。
本記事では、試験内容や合格率の推移、受験資格や申込の流れについてご紹介しました。ご紹介した情報を参考にしながら、自分に合った学習方法で準備を進めていきましょう。
また、保育士資格を取得した後は、働き方を考えることも大切です。保育士人材バンクでは、解答速報の配信をはじめ、試験後の就職活動やキャリア形成に役立つサポートをおこなっています。
受験勉強だけでなく、その先のキャリアまで見据えて行動していくことで、保育士としての第一歩をより安心して踏み出せるはずです!