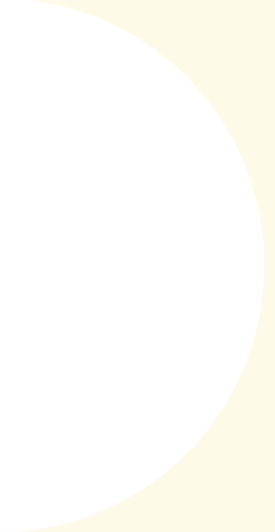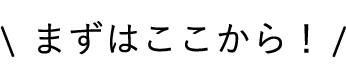「給料が安い」「労働時間が長い」など、大変なイメージを持たれがちな保育士の仕事。
しかし、2019年に始まった働き方改革では、政府や自治体が保育士の“働きやすさ”を改善するべく、さまざまな施策を取り入れました。
くわえて、保育士資格は保育園だけでなくさまざまな職場で働けるのも魅力の1つです。
本記事では、保育士の働き方について6つのパターンに分けて解説していきます。
資格を活かした働き方に悩んでいる方や現在保育園などに勤務されていて、転職を考えている保育士さんは、ぜひ参考にしてみてください。


働き方の特徴
働いている保護者に代わって、子どもたちの生活や成長をサポートする保育士の仕事。
ここでは、保育士の働き方について特徴を詳しくご紹介します。
幅広い雇用形態で働ける
保育士は、正社員のみならず、パートや派遣など幅広い雇用形態で働けます。
保育士資格があれば、正社員でクラス担任として働くこともできますしパートで保育補助として短時間などで働くこともできます。
結婚や出産、転勤などライフスタイルの変化に合わせて、柔軟に働けるのは魅力の1つです。
多くの園がシフト制を採用
保育園の開園時間は7時〜19時や7時30分〜20時30分などさまざまです。
その中で、保育士は1日8時間働くため、多くの園ではシフト制を導入しています。
固定シフトで働くケースもありますが、「早番」「中番」「遅番」といわれるシフトで働く形が多いでしょう。
後ほど詳しく解説しますが、シフトによって勤務時間はもちろん、業務内容も変わってきます。
土曜日出勤になることもある
保育施設は月曜日から土曜日まで開設している場合が多いため、その分、保育士も出勤になることもあります。
土曜日はお仕事が休みの保護者が多いため、登園する子どもの人数は少ない傾向にあります。
それにより、保育士は月に1~2回程度、交代で土曜日に入るケースがほとんどです。
土曜日が出勤の場合は、その分、平日に休みが入ることがあります。


【雇用形態別】保育士の働き方
ここでは、常勤、非常勤と雇用形態別に保育士の働き方をご紹介します。
保育士の働き方①【常勤】
パートでも一定の条件を満たすことで常勤となる場合がありますが、
正社員が常勤と呼ばれることが多くあります。
常勤保育士の働き方は、1日8時間の週5日勤務ですが自治体によっては、1日6時間以上または月20日以上勤務する場合に常勤保育士と定義されることもあります。
常勤保育士の仕事内容としてはクラスの担任や副担任を任されることが多くあります。
クラス運営や保護者対応、行事の担当や指導案の作成など仕事内容は多岐に渡ります。
常勤保育士の給料形態は、月給制がほとんどで、園によってはボーナスが支給される場合もあります。
参考:内閣府子ども・子育て本部「短時間保育士及び常勤保育士の取扱いについて」
保育士の働き方②【非常勤】
非常勤保育士は、パートタイムやアルバイトなど、正社員以外で働く保育士を指すことがほとんどです。
非常勤保育士の勤務時間は、8時間より短く、
たとえば、1日に5時間、週3回勤務など、労働時間は常勤に比べて短めです。
非常勤保育士の働き方は、比較的自由にシフトが組めて、自分の都合に合わせて柔軟に働けるのがメリットといえます。
また、非常勤保育士は、常勤保育士のサポート役として、保育補助や雑務をする仕事が多いでしょう。
給料は時給制で、働いた分だけ給料が発生する場合が多いでしょう。
【シフト別】保育士の働き方
ほとんどの保育園がシフト制を導入していると前述しました。
ここからは具体的に、シフト別の働き方を見ていきましょう。
保育士の働き方①【早番】
早番の勤務時間は、7時台〜16時台の前後時間が一般的です。
保育園によっては、7時から子どもを受け入れる場合もあるため、その場合は開園の10~15分前には出勤して準備を整える必要があります。
朝は早いですが、その分終わる時間も早いため、退勤後に自由な時間を多くとれることがメリットです。
仕事内容の一例としては、掃除を含む開園準備、子どもの受け入れ・保護者対応、受け入れ時の情報を担任に引き継ぐことなどが挙げられます。
プール(水遊び)がある夏場は、朝から水をプールにためはじめる園もあるでしょう。
保育士の働き方②【中番】
園によって中番の勤務時間はさまざまですが、
一例として8時~17時、9時~18時などがあります。
子どもたちが一番多くいる時間帯なので、保育士の人数も一番多いシフトです。
朝の様子や体調など、早番から必要な情報を引き継ぎ、クラスごとに活動をはじめます。シフトの中では、メインの時間帯を担当することが多くあります。
退勤前には、体調面や活動の様子などを、遅番の保育士へ引継ぎするのも大切な仕事です。
中番は、早番ほど朝が早すぎず、退勤時間も遅すぎないので、働きやすい時間帯といえるでしょう。次の日が早番でも無理のない生活ができます。
保育士の働き方③【遅番】
遅番の勤務時間の一例としては、10時~19時、または11時〜20時などがあります。
遅番勤務の保育士は、夜の延長保育を利用する子どもたちを保育するのが特徴です。
また、早番、中番の保育士から引き継いだ連絡事項を保護者に伝えたり、降園後に掃除や戸締りなど閉園準備をしたりするのも大切な仕事です。園にもよりますが、夕食提供や夜の補食提供をすることもあります。
遅番は帰りの時間が遅めですが、ゆっくり出勤できるのがメリットです。
朝が苦手な方や、午前中に他の用事を済ませたい方には、ピッタリの働き方といえます。
【施設形態別】保育士の働き方

保育士資格や、経験を活かして働ける職場はたくさんあります。
ここでは、施設形態別に保育士の働き方をご紹介します。
保育士の働き方①【保育園・保育所】
保育士の職場というと、保育園を一番にイメージする方も多いかもしれません。
保育園は乳児から就学前までの年齢を対象に、保育を必要とする子どもを預かる施設です。
保育園とひとくちにいっても、認可保育園、認可外保育園、院内保育所、企業内保育所などとさまざまな種類があります。
求人数も多く正社員やパート、契約社員などさまざまな雇用形態があるため保育士資格を活かしてライフスタイルに合った働き方ができます。
保育士の働き方②【病児保育室】
病気などで保育園に登園できない子どもを預かる『病児保育室』も、保育士の資格や経験を活かして働ける職場です。
病児保育室で働く保育士は、具合が悪い子どもに寄り添いつつ、保育をしながら書類の記入などをおこないます。服薬の管理、感染症対応は施設や自治体によって異なる場合があります。
少人数制が多いので、子どもとしっかり向き合いたい方におすすめの働き方といえます。
室内で静かに過ごす場合が多いので、体力的な負担が少ないのもメリットです。
保育士の働き方③【学童保育】
小学校1年生から3年生までの子どもが、放課後や長期休みに過ごす『学童保育』でも、保育士として働くことができます。
近年は、共働き家庭が増えているため学童保育のニーズが高まっています。
勤務時間は、平日は11時頃から20時頃まで、土曜日や長期休みの場合は朝早くから勤務することもあります。
平日は遅い出勤が比較的多く、家庭やプライベートと両立しながら働けるのがメリットです。小学校が夏休みなどの長期休暇を除いては、保育園よりも比較的固定された時間で働くこともできます。
保育士の働き方④【児童発達支援・放課後等デイサービス】
障がいのある子どもの中でも主に未就学児を対象としている「児童発達支援」や、小学校就学〜18歳(状況により変動)を対象としている「放課後等デイサービス」でも保育士資格を活かして働くことができます。
近年障がい児を対象とした施設のニーズが社会的に高まっており、利用する子ども(児童)数が増えている施設形態です。
国の制度も整備が進んでおり、近年では保育士を配置することで事業所に「加算」が入る仕組みも施行されました。
各施設の定位は10名前後である事が多く、保育園と比べると少人数で子どもとじっくり関わることができるでしょう。
保育園などで培った知識や経験を活かしやすいといえる施設形態です。
保育士の働き方③【児童福祉施設】
保育園も児童福祉施設の1つですが、ほかにもたくさんの児童福祉施設があり、保育士資格や経験を活かして働けます。
保育園以外の児童福祉施設は下記のとおりです。
- 乳児院
- 児童養護施設
- 助産施設
- 母子生活支援施設
- 児童厚生施設
- 知的障がい児施設
- 知的障がい児通園施設
- 重症心身障がい児施設
- 盲ろうあ児施設
- 肢体不自由児施設
- 情緒障がい児短期治療施設
- 児童家庭支援センター
- 児童自立支援施設
児童福祉施設で働く保育士は、『施設保育士』とも呼ばれ、保育士資格が必須になることがあります。
仕事内容は施設によってさまざまですが、子どもたちの日常生活の介助や、自立に向けたサポート、保護者支援などです。
働き方は、シフト制である場合が多く、夜勤、休日出勤が必要な施設もあります。
児童福祉施設は責任もあり大変な職場が多いですが、その分、やりがいも大きく、保育士としてのスキルアップも狙えます。


【併用資格別】保育士の働き方
保育士資格だけでも活躍できる職場は十分ありますが、加えて持っていると、活躍の場が広がる資格がいくつかあります。1つずつご紹介していきます。
保育士の働き方①【幼稚園教諭】
幼稚園教諭は、満3歳から小学校入学までの子どもたちに対して教育をおこなうための資格です。幼稚園教諭の資格をもっていれば、幼稚園で働くことができます。
また、保育士資格と併用することで、保育園と幼稚園が一体化した『認定こども園』でも活躍できます。
幼保連携型*以外の認定子ども園であれば、保育士資格のみで働ける場合もありますが、併用して幼稚園教諭ももっていた方が望ましいでしょう。
*幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ
参考:厚生労働省 『幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭に係る保育士資格取得の特例について』
保育士の働き方②【英語検定】
保育士と併用して、英語検定をもっていると、インターナショナルスクールでも一層活躍できます。
インターナショナルスクールとは、英語保育をおこなう施設のことで、英語を母国語とする子どもたちの保育をおこないます。
インターナショナルスクールで働く場合、保育士資格にくわえて、英語検定などを取得して英語の教養を身に付けておくと活躍の場が広がります。
また、英語検定以外にも、下記の資格があればインターナショナルスクールで活躍できる可能性があります。
- 幼児教育・保育英語検定
- TOEIC
- J shine資格
【役職紹介】保育士の働き方

役職によっても保育士の働き方は変わってきます。
これまで、保育園の役職は、主任保育士と園長しかありませんでした。
しかし、2017年4月に始まった『処遇改善加算Ⅱ』によって、新たに3つの役職が加わりました。
それにより、若手保育士も段階的にキャリアアップを目指せるようになりました。
ここでは、役職の働き方についてそれぞれ詳しく解説していきます。
保育士の働き方①職務分野別リーダー
役職がない保育士が、最初に就任できるのが、『職務分野別リーダー』です。
下記6つの中から専門分野を選び、研修を受講します。
- 乳児保育
- 幼児教育
- 障害児保育
- 食育・アレルギー対応
- 保健衛生・安全対策
- 保護者支援・子育て支援
研修を含む下記の要件を満たすことで、その分野に特化したリーダーとして役職に就くことができるでしょう。
- 保育士の経験年数がおおよそ3年以上であること
- 担当する職務分野の研修を修了すること
- 職務分野別リーダーとして職場から発令を受けること
職務分野別リーダーに就任すると、研修で身につけた専門スキルを活かして、他の保育士へ指導やアドバイスをおこなう役割を担います。
なお、各園によって金額は異なりますが、職務分野別リーダーは約月額5,000円の加算手当がもらえます。専門スキルを磨き、給料アップが狙えるのは大きな魅力です。
参考:厚生労働省 『保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ』
保育士の働き方②専門リーダー
職務分野別リーダーの次に目指せるのが、『専門リーダー』です。
下記の要件を満たせば、専門リーダーとして現場で活躍することができます。
- 保育士の経験年数がおおよそ7年以上であること
- 職務分野別リーダーの経験があること
- 4つ以上の分野の研修を修了していること
- 専門リーダーとして職場から発令を受けること
専門リーダーは、保育士としてより高い専門性や現場を引っ張っていくリーダーシップが求められる役職です。
役職手当は、最大で月額40,000円支給されるため、就任することで大幅な給料アップが期待できるでしょう。なお支給金額は園によってさまざまです。
参考:厚生労働省 『保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ』
保育士の働き方③副主任保育士
ライン職と呼ばれ、保育現場の総括的な役割を担う役職が、『副主任保育士』です。
主任保育士のフォローや、現場から出た声を責任者にあげるのが主な役割です。
一言でいうと、現場と責任者の橋渡し役的なポジションになります。
必要な要件は次のとおりです。
- 保育士の経験年数がおおよそ7年以上であること
- 職務分野別リーダーの経験があること
- マネジメント+3つ以上の分野の研修を修了していること
- 副主任保育士として職場から発令を受けること
参考:厚生労働省 『保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ』
保育士の働き方④主任保育士
主任保育士は、園長の補佐役として園をまとめる、保育現場で責任あるポジションです。
保育全体の司令塔として、マネジメント業務も担います。
主任保育士になるために必要な経験年数は決まっていませんが、全国保育協議会の調査によると、平均勤続年数は20〜30年未満でした。ただし、園の規模やタイミングによってはもっと早くから着任している方もいるでしょう。
参考:全国社会福祉協議会『全国保育協議会会員の実態調査2021報告書』
保育士の働き方⑤園長
園の最高責任者である園長は、施設全体の運営と管理を担います。
最高責任者である分、責任も大きいですが、給料も高くやりがいもあるため、最終的なゴールとして目指したい方もいるでしょう。
「理想の保育園をつくりあげていきたい」という方にはピッタリの役職です。
一般的には、10年以上の保育経験が必要とされていますが、園によってさまざまです。
1ヶ月の給料は、公立保育園の場合が545,089円、私立保育園は541,003円程度という調査結果が出ています。
参考:厚生労働省『幼稚園・保育所等の経営実態調査結果 』
【保育士の将来】保育士の働き方
保育士の方の中には、「給料が低い」「仕事が多い」という不満を抱えていたり、将来的に続けられないと感じて辞めてしまう人もいるでしょう。
中には将来的なことを考えて、他業種へ転職したりする方もいるかもしれません。
しかし、保育士の働き方は徐々に改善されてきています。
近年は、核家族が増えたことや、待機児童問題など社会的な背景により、国は保育施設を増やす取り組みをおこなっています。
それに伴い、保育士の需要はさらに高まってきています。
また、国や自治体は、保育士の処遇を改善するための制度を作ったり、ICTシステムを導入して業務負担を減らしたりと、働きやすさのために力を入れてきています。
さらに、今回ご紹介したように、保育園以外にも資格を活かせる職場はたくさんありますし、働き方の選択肢も増えています。
もしこれから保育士として将来的にどうするか、悩んでいる方、迷っている方は、幅広い選択肢の中から自分に合う働き方を探してみてはいかがでしょうか。
保育士の働き方まとめ
保育士の働き方について、詳しくご紹介しました。
保育士は専門性の高い職業であり、将来的にもさらにニーズが高まっていくことが考えられます。
保育士資格を活かせる職場や、働き方の選択肢はたくさんあります。
もし、「保育士として自分らしく働きたい」「キャリアアップできる保育園へ転職したい」など、働き方に悩みや不安を抱えている方は、保育士人材バンクへご相談ください。
保育士専任キャリアパートナーが、悩みや希望を踏まえて、あなたにとって最適な選択をご提案いたします。
転職活動で必要になる書類の添削や、面接対策などもしっかりサポートいたしますので、転職活動が不安な方もご安心ください。

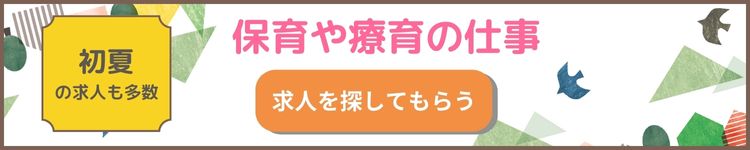





を利用するメリット・デメリットは?【保育士人材バンク】-1-scaled-e1726015306357.jpg)